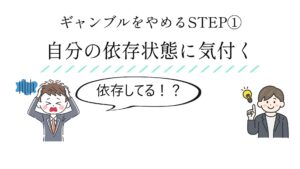パチンコ・スロットをやめたい方へ
こんにちは、「ゆるやめ」管理人のひろのぶです。
この記事では15年ギャンブル依存症だった私自身がパチンコ・スロットから抜け出した道のりを、9つのステップで解説しています。
同じように悩んでいるあなたの、脱出の手助けになれたら嬉しいです。
- 無理なく楽にギャンブルをやめる方法8ステップの流れ
- 1人でも実施が可能な方法
- サポートを受けたい場合の案内
書いた人
私は40歳まで工場で機械保全士として働いていましたが、その裏でギャンブル依存症に苦しんでいた時期があります。
毎日時間があれば行きたい気持ちになり、とにかくパチンコ屋に向かっている自分がいました。
「やめたい気持ちはあるが、どうしてもやってしまう」
「負けた日は自己嫌悪と後悔を繰り返して、イライラが止まらない」
「それでもいつかやめられるタイミングが来るだろうと諦める」
そんな日々が続いていたのです。
その頃はどうしてこんなことを繰り返してしまうのか、自分でもわからず悩んでいました。
 保全士:ひろのぶ
保全士:ひろのぶですがそんな私でも無事ギャンブルをやめることができました!
このブログでは過去の自分にぜひ読んで欲しい!!
──という敵わぬ願いを、せめて同じように困っている方の役に立てばと書いたものになります。



ちなみに結局のところ根性論や精神論でやめたのかな?



我慢が出来ないのは根性が足りないから、精神が弱いから、意思が弱いから、そんな人によって左右される不確かなものには頼りません。(私はそれではやめれませんでしたので…)



自分にもできるかな…?



私は設備保全士として現実的な視点と論理的な思考がベースになっています。そのため今回の方法も脳科学や心理学の知識を踏まえて原因を追究して、対処マニュアルのように作っていますので安心してください。
【サポート】専門機関に頼ってもいい
まず記事の内容解説前に、可能であれば専門機関に頼ることをオススメします。
ギャンブル依存症から抜け出すことは1人でやらないといけない理由はなく、サポートを受ける方が効果的です。まずは一度誰かに相談してみるという選択肢も立派な“脱出ルート”です。
相談できる公的機関のリンク
以下は、厚生労働省が提供している依存症対策の公式ポータルサイトです。
全国の相談窓口・医療機関の情報も掲載されています。
- 各都道府県の専門窓口や相談機関の一覧あり(外部リンク)
- 匿名での相談も可能(自治体によって対応形式は異なります)
- 家族の方も相談できます
自助グループ
自助グループとは、同じ体験を持つ人が仲間の体験を聴き、自分の体験を語り、互いに支え合うグループです。ギャンブルの自助グループには、例えばGA(ギャンブラーズ・アノニマス)などがあります。
費用は献金のみですが、場所と時間が決まっていますのでスケジュールが合う方は参加してみるのも良いでしょう。
【考え方】ギャンブルをやりたいと思わないようになる
結論から言うとギャンブルを我慢に頼らず緩くやめる為には
「ギャンブルをやりたいと思わない」ようになることです。
ここからこの理由をいくつか説明させてもらいます。
心と体はやりたがっている



「すでにやめたいと思っているけど?」
私もそうだったのですが、「やめたい!やめたい!」と思いながらもギャンブルを「やりたい!!」と“心や体が思っている”ということです。
その結果いつまでもギャンブルをやりたい気持ち、「ギャンブル衝動」が生まれてしまいます。



自分の考えと心は別物ということです。
我慢を強いられる
また、よくある「お金を持たない、パチンコ屋に近寄らない」といった物理的な対策ですと、
物凄い我慢を強いられることになります。
そしてこの我慢が可能ならみんな辞められているわけですが、それが出来ないのでやめられない。
ですので我慢に頼らない方法が有効となります。
我慢に頼らない方法
“我慢”を最小限に抑えて楽にやめられるようになる、その為に目指す目標が「ギャンブルをやりたいと思わない」ようになることです。
そしてそれを可能にする為の方法がこの後で解説する“9つのステップ”になります。



ギャンブルをやめることは、機械設備を直すことにかなり似ています。
ギャンブルをやりたい = ギャンブル回路が作られている状態で、他のどの回路より優先されているようなもの。



回路を一つ一つ読み解いて対策の仕組みを作って行くことで設備(人)にかかる負荷(我慢)を最小限に抑えることができるよ!
詳しい記事は下記をご覧ください
【対策】9つのステップ
ここからは対策9ステップの概要を解説していきます。この記事はステップの全体像を把握してもらうためのものです。各ステップの詳細に関してはボリュームがありますので、別の記事に分けて解説しています。
全体のステップ
全体のステップは下記になります。
- 依存症について理解する①
- まずは依存の状態に気付く
- 依存症について理解する②
- 依存の原因を知り、対策の知識を付ける
- 環境を整える①
- 自分の依存行動パターンを見える化
- 環境を整える②
- 依存に負けない環境を整える
- 新しい活動
- 活動を習慣にして育てていく
- しきい値を下げる
- ルールを決める
- 改善サイクル
- 新しい生活サイクルを徐々に始める
- やめてみる
- やめるチャレンジ
- スリップ対策(再発防止)
- 心構えと対策
各ステップの解説の前に、一つ注意点があります。
進め方
このステップは「①を完璧にこなしてから②へ進む」というようなステージクリア型の進め方ではありません。
むしろ、全体を少しずつ進めながら、⑦の「改善サイクル」内で何度も振り返っていく前提のスタイルになります。
たとえば…
最初の①や②で扱う「依存症についての理解」は、読めばすぐにすべてを理解できるものではありません。
ただし、ここを飛ばして行動だけを始めてしまうと、
- 「なぜこれをやっているのか」
- 「本当に意味があるのか?」
と疑問が湧いてしまい、モチベーションが下がったり、効果を感じられなかったりすることがあります。
また、後半のステップを進めていく中で、
「あ、前の内容に戻って対策したほうがいいかも」
という新たな気づきや再確認の必要性も自然と出てきます。
そのため、ステップはあくまで「この順番の方が理解しやすいかな」という参考程度で、絶対にこの順番どおりに進める必要はありません。
おすすめの進め方
おすすめの進め方としては…
- まずは全体をざっくり読んで流れをつかむ
- 気になるところから軽く取り組んでみる
- うまくいかない/わからない部分は改善サイクル(⑦)で何度でも調整する
こういったゆるやかな循環スタイルの方が、継続しやすく結果的にやめることにつながりやすいです。
ですので
「1日で1つずつ絶対やる」ではなく
「1週間で3つ試してみる」くらいの軽いペースでもまったく問題ありません。
今回の記事は、まず全体像をざっくり把握してもらうことを目的にしています。
細かく完璧を目指すより、まずは“進めながら振り返る”スタイルで少しずつ整えていくつもりで読んでみてください。自分にとって足りない部分は、その都度⑦の改善サイクルで見直していけばOKです。
ではここから、各ステップを一つずつ、順を追って解説していきます。
【STEP1】まずは依存の状態に気付く
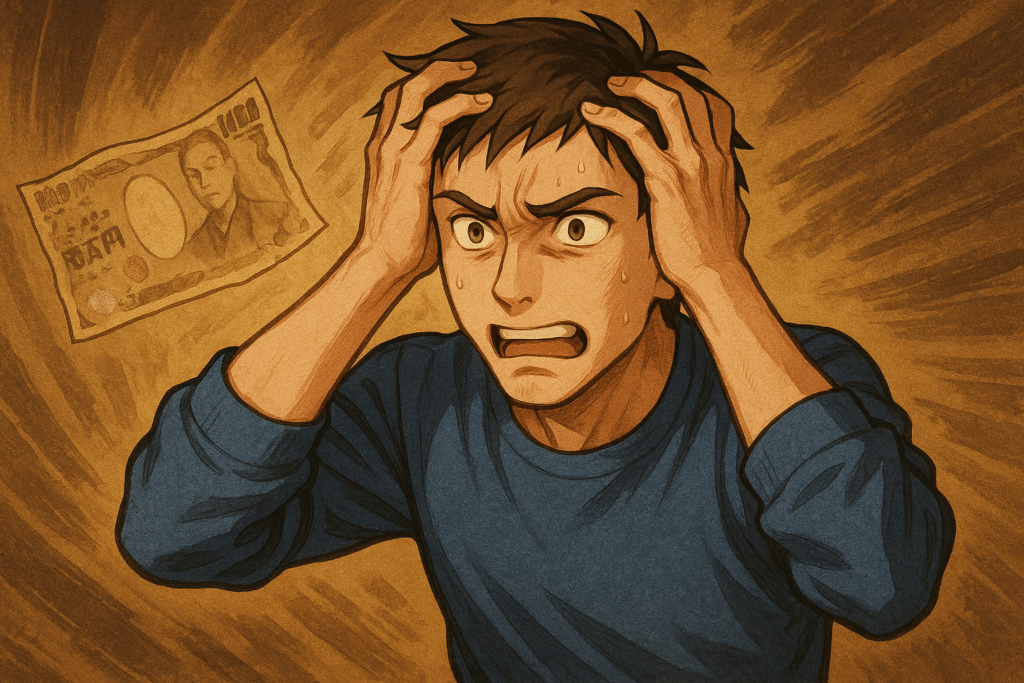
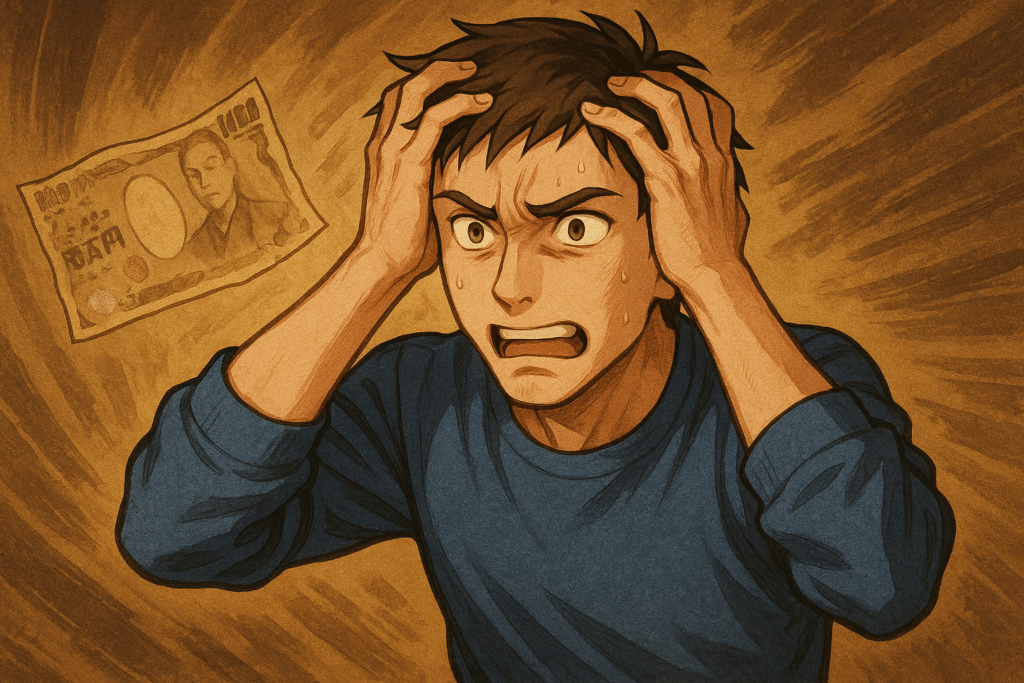
STEP1ではそもそも自分がどれくらい依存しているのか“自分自身の状態に気付く”ことが目的になっています。
たとえば
「やめたいのにやめられない…」
「生活費が足りない…」
「誰にも言えない…」
このような自分の思いと行動や思考が違うという“違和感”に気付くこと。
依存症は自分では「まだ大丈夫」と思いがちですが、他人から見たらすでに問題になっているかもしれません。
自分は問題を深刻に受け止めきれていない、そのことに気付くことがスタートです。



機械では、故障や異常は日常点検時などの「違和感」によって発見されます。最初に音や振動に“気づけるか”どうかが、大切なポイントです。これに気づけないと設備の状態は徐々に悪化してしまいます。
気付くのが遅いと…
そして気付かない結果「行くところまで行く」という方が多いです。
たとえば
- 借金をして返済の目途がつかない
- 友人や家族からも見放されてしまった
- 仕事に影響が出てもう来なくていいと言われた



そして僕の場合は依存症15年、損失金額総額1000万以上、さらに借金200万してようやく気付きました…。
このようにもう本当に限界だと“底付き”を経験しないと“気づかない”という場合があります。
底付きがきっかけになる
このようにもう本当に限界だと、“底付き”を経験しないと“気づかない”という場合があります。



たとえば、機械で言うと“底付き”はメンテナンスせずに悪化して、重大故障で強制停止、工場の生産が完全停止してお手上げの状態だよ!!



だからこそ問題の解決に手を入れるきっかけになるわけですが、可能ならその前に気づきたいものです。
気付くことが最初のステップ
この記事を読んでくれているみなさんには私と違い、出来れば底付き前に気づいて欲しい。
だからこそSTEP1でまずは「気付くこと」が最初のステップになります。
ここからいくつかSTEP1の気付く為の方法をいくつか解説していきます。
詳細に関しては各個別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
【1】パチンコは問題を受け止めるとやめられる
【2】本当に「お金が目的」なんですか?
概要【クリックで展開】
ギャンブルの目的が「お金を稼ぐこと」だと感じている人は多いと思います。
でも──もし本当に稼げているなら、負けた瞬間にやめられるはずです。
実際はどうでしょうか?
「勝てそう」「あと1回で…」という幻想や錯覚に支配されていることが多く、
それはもはや“金銭目的”ではなく、刺激依存や感情の反応に変わってしまっている可能性があります。
この項目では以下の視点から「金銭目的の正体」に迫ります
- 金銭目的かどうかのセルフチェック
- 金銭目的と依存的目的の違い
- 目的がズレていくメカニズム
「本気でお金が目的だ」と思う方こそ、一度冷静に立ち止まって考えてみてください。
詳しい記事は下記をご覧ください
【3】ギャンブルでストレス解消が目的?
概要【クリックで展開】
最初は娯楽だったはずのギャンブル。
でも今は、「ストレスが溜まってくると行きたくなる」「やってると安心する」──そんな感覚、ありませんか?
これは、脳が“やっている時が普通”だと錯覚している状態です。
そして、ギャンブルをしていない時間に“不快”を感じるようになっているなら、それはもう立派な依存症のサイン。
この項目では次のようなことを整理できます
- 遊び→逃避目的への変化に気づくセルフチェック
- 目的がズレていくプロセス
- 快楽から「不快の解消」へと価値観がすり替わる理由
今のあなたの“目的”は、本当に当初と同じですか?
一度、自分の中で立ち止まるきっかけにしてください。
詳しい記事は下記をご覧ください
【4】ギャンブルをやめる目的は何ですか?
(制作中です!)
【STEP2】依存の原因を知り、対策の知識を付ける
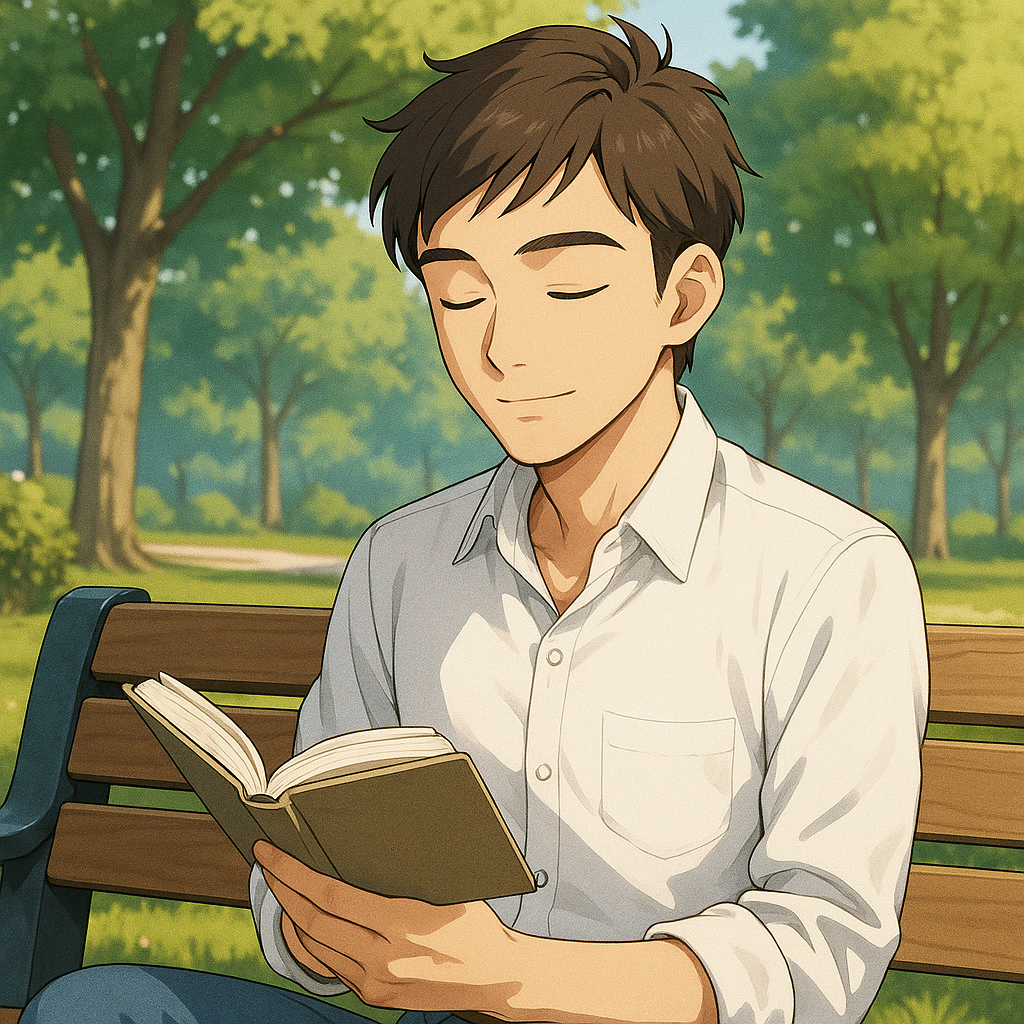
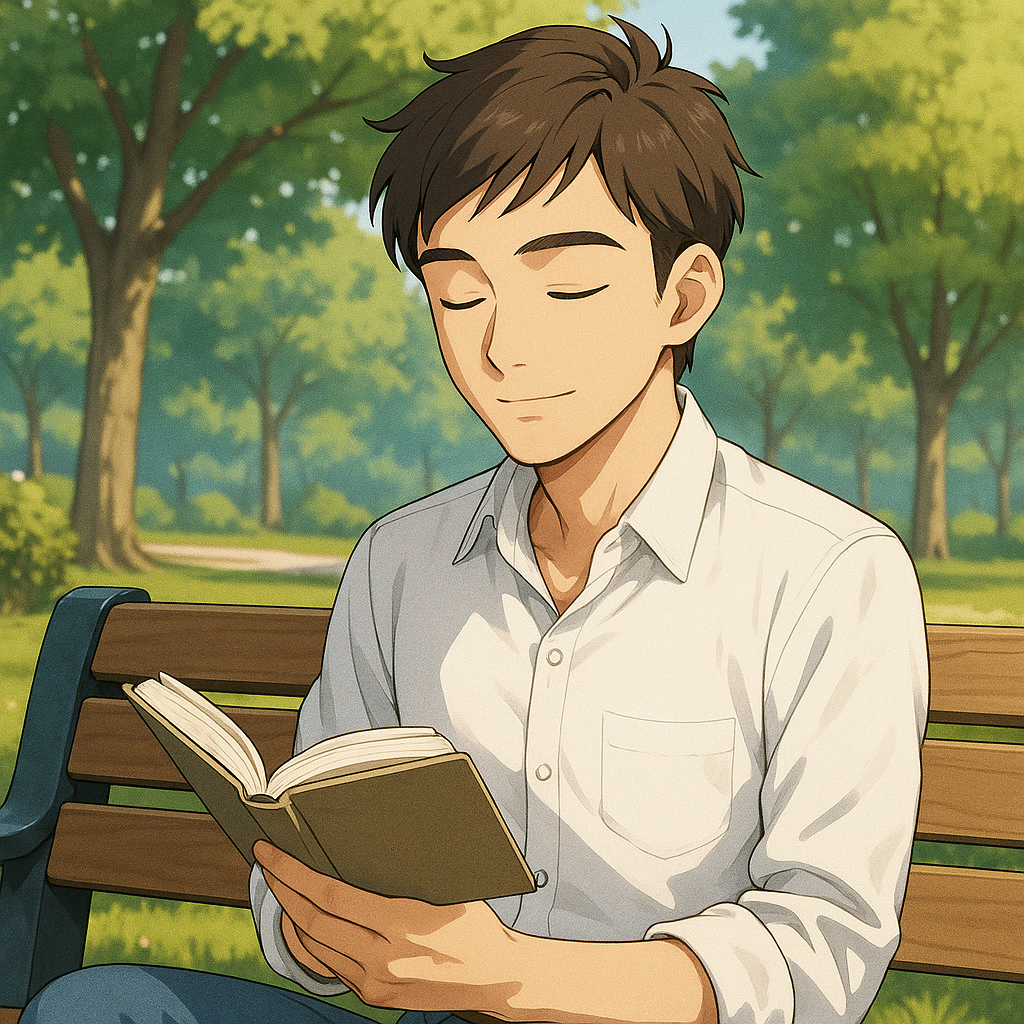
STEP2ではなんでギャンブルをやめられないのか“正しい知識を学習する”ことが目的になっています。
たとえば
「自分は意志が弱いのかもしれない…」
「どうしていつもやめられないんだろう…」
「あの人が誘うから悪いんだ」
このような自分をいつまでも責めてしまう、また他人に責任を押し付けてしまうという“否定”を防ぐことができます。
そしてやめるために何をすればいいのかを知ることで、やめようやめようとギャンブルに行かない努力をして我慢を繰り返して失敗して、ストレスを溜めてまたギャンブルにのめり込むといった“悪循環”を止めることができます。
ギャンブル依存と依存症
概要【クリックで展開】
ギャンブル依存症は甘えや意志の弱さの問題ではありません。
ただ依存と依存症で何が違うのかよく分からない。
この項目では…
- なぜやめたいのにやめられないのか?
- その理由として依存と依存症では具体的にどのように違うのか?
これらを解説しています。
詳しい記事は下記をご覧ください
3つの要因(主な原因)
上記でも同様のことを書いているのですが、
ギャンブルを我慢に頼らずやめる為には「ギャンブルをやりたいと思わない」ようになることです。
そしてそれは3つの要因が元になっています。
- 依存対象がある
- 依存仲間がいる
- 本人がやめたいと思わない
他にも脳が我慢に耐えられない理由など、これらを解説しています。
詳しい記事は下記をご覧ください
対策の知識
依存から抜け出す為に必要な知識である人間の行動原理について知ることで、無理なく徐々にギャンブルから抜け出すことができます。
STEP2では、依存の原因と対処方法を「科学と構造」で紐解き、
感情的な悪循環する後悔を「論理的な納得」に切り替えることを目指します。



機械では、制御装置が指示を出しても、センサーやブレーキが壊れていたら機械は正しい判断をしません。
依存も“理性が届かない状態”になっているだけなんです。
ここからいくつかSTEP2の正しい知識についていくつか解説していきます。
詳細に関しては各個別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
①やりたくなるのは“期待”してしまうから
- 当たりそうな期待感 → 快感物質「ドーパミン」分泌
- 演出や音による五感刺激 → 快感記憶が強くなる
- ギャンブルは手軽な快感ですぐ得れるから
詳しい記事は下記をご覧ください
②続けてしまうのは胴元の仕組み
ギャンブルは脳の「判断ミス」を誘発するように仕組まれています。
その代表が“もう一回だけ”と思わせる錯覚です。
それは「自分が悪い」わけではなくバイアス(脳の仕組み)と胴元が仕掛けた設計の掛け算で やめられなくなるよう仕向けられています。
詳しい記事は下記をご覧ください
③ブレーキが弱まっている
私たちの「意思決定」や「感情制御」をしている脳のブレーキは疲労やストレスに弱く、またギャンブル依存症になると変化して機能が低下する可能性があると研究で分かっています。
その結果
- 「感情を抑える制御力」
- 「今、やるべきことをやる集中力」
- 「やりたくないことを区別する判断力」
といった理性が必要な力が弱まってしまいます。
これが「やめたいと思っているのに、やってしまう」行動に繋がり、ギャンブルがやめられない要因になります。
詳しい記事は下記をご覧ください
④依存は自動化されている
ギャンブル依存症と聞くとやっかいな症状ですが、これは日常生活で例えるなら生活水準が上がっているようなものです。
日常生活では移動するのに電車がある、食事をするのにコンビニがある、このような便利な仕組みが生活水準を上げています。
ギャンブルでは手軽にやりやすい場所にある、手の届く価格設定、そしてこのような仕組みが「快楽の水準を上げる」
そして上がった水準は維持しないと「今更出来ないのは不便」だと思い不快になります。不快を解消するためにまた快楽を求めて、手軽にやれるギャンブルに手を出します。
そしてこのような仕組みが整った環境がトリガーやスイッチと呼ばれるきっかけを作り、ギャンブルがやりたくなる頻度がどんどん増えていきます。
ギャンブルをやめるにはギャンブル衝動が起こるきっかけを減らし、この「自動化」を防ぐことが重要になります。
詳しい記事は下記をご覧ください
⑤やりたくなる強さの源
ギャンブル依存症になるとギャンブルをやっている時が、自分にとって自然で安心できる、出たくない安全な領域だと心が思うようになっていきます。
その結果そこから出たくないと思ってしまい、逆にギャンブルをやっていない時に“不快”だと感じるようになっていきます。
つまり現状の不快感を取り除く為にギャンブルをやっているということになります。
ですが現実では金銭・人間関係トラブルなど問題が起こって周囲の人や、ギャンブルをやっていない冷静な時の判断としてはもうやめたいと考えだすわけです。
それでもギャンブルをやらない不快な状態を脳は解消したいと考える為、やらないという「不快」を長期間我慢することは難しいと言えます。
詳しい記事は下記をご覧ください
対策には「我慢に頼らない方法」が必要
【STEP3】自分の依存行動パターンを見える化


STEP3では自分自身の思考と行動パターンを把握して“行動パターンの見える化”をすることが目的になります。
たとえば
「気づいたら行きたくなっている」
「絶対やめると思った次の日には行きたい気持ちがある」
「今度こそやめると決意したけどやっぱりあらがえない」
──そんな経験、ありませんか?
依存行動の多くは、無意識のパターンとして繰り返されています。
STEP3では、自分の思考や行動を「記録」し、行動パターンの「見える化」をすることで自分の取り扱い説明書を作ることを目指します。



機械では、故障した設備の図面を見直す作業です。見える化していない状態は図面がない状態で設備を直すようなもの。
“ギャンブル回路の接点を洗い出す”ことが、整備のスタートラインになります。
ここからいくつかSTEP3の見える化についていくつか解説していきます。
詳細に関しては各個別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
①どうして記録が必要なのか?
ギャンブルに行くまでの流れは、
「思考」→「感情」→「行動」 というプロセスで成り立っています。
でもこの流れは、繰り返されるうちに自動化(=クセ)され、意識する間もなく動き出してしまいます。
そこで記録をすることで、自分の中の“反応パターン”を外から観察できるようになります。
認知行動療法(CBT)では、依存行動の前にどんな思考や感情が起きているかを記録することが効果的と言われています。
たとえば、こんな記録を残す
- 「今日はなぜ行きたくなったのか?」
- 「どんなきっかけでスイッチが入った?」
- 「そのときの気持ちは?」
紙でもスマホでもOKです。
これを記録することで、自分の思考や行動のパターンを見える化し、冷静に理解することができます。



機械には「安全柵で設備を囲う」、「緊急停止ボタン」など安全装置がついています。
依存にも“衝動を止める仕掛け”が必要です。
詳しい記事は下記をご覧ください
②トリガーを回避すれば「スイッチが入る瞬間」を減らせる
ギャンブルを抜け出すために必要なことの1つは、“行きたいと思う回数”を減らすこと。
その為には行きたいと思う“ギャンブル衝動”に繋がるスイッチが入る瞬間を減らすことが必要になってきます。
そしてこのスイッチは残念ながら無くすことは出来ません。
ですので「このスイッチをどうやって無くすか」ではなく、スイッチが入らないように、“先にトリガーと呼ばれるきっかけを減らす”ことが重要になってきます。
トリガーを減らすことで、自然と「行きたいと思う回数」そのものが減っていきます。
詳しい記事は下記をご覧ください
③スイッチを“押さなく”する
ギャンブル依存症になるとトリガーやスイッチと呼ばれるきっかけでギャンブルがやりたくなります。
たとえば
- 仕事帰りに疲れて、とりあえず行くかとホールに入る
- → 疲れ【トリガー】+帰宅ルート【トリガー】=【スイッチON】
- 何かにイライラしたあと、無性にパチンコで発散したくなる
- → ストレス【トリガー】+時間に余裕がある【トリガー】=【スイッチON】
流れとしては下記になります。
トリガー(1個以上) → スイッチON → 脳が自動で快感を欲求 → ギャンブル衝動!!
そしてこのギャンブル衝動=ドーパミンが分泌している状態ということです。
このスイッチを消すことは難しいため、スイッチを押さないことが大切になってきます。
詳しい記事は下記をご覧ください
④行動のやる気・モチベーションには“報酬”が必要
私たちが自然に動けるのは、「楽しい」「得する」と脳が感じたとき。これがやる気の源として「報酬」になります。
ギャンブルを「やめなきゃ」だけでは得られむものがイメージしづらく、モチベーションが続かないし行きたくなる気持ちになってしまいます。
こんな「行きたくなる気持ち」を「行ったらもったいない気持ち」に変える為に有効な手段として、「今やめたら手に入るもの」などを数字やイメージで“見える化”する方法があります。
具体的に手に入るものが報酬となり、無理矢理やる気を出すのではなく“納得と期待”で動けるようになる。また報酬は自然と目に入るようにすることで意識しますし、一番重たい最初の一歩を行うやる気を生み出すことができます。
その為に一度自分の
- 「やめたら手に入る報酬」
- 「欲しいものリストを作成」
- 「達成したら○○を買う」
など報酬を一度考えてみましょう。
そして最終的には報酬を意思しなくても「この活動には報酬があるんだ」と“自然とやる気が湧く”ようになります。
詳しい記事は下記をご覧ください
【STEP4】依存に負けない環境を整える


STEP4ではSTEP3で把握した自分の行動パターンからギャンブルに繋がらないように“仕組みで回避する環境”にすることが目的になります。
STEP3でせっかく自分の取り扱い説明書を作っても活用しなければもったいないです。
自分は〇〇の時にギャンブルをやっていると分かったらそこで我慢する、ではなく「仕組み」で対処するのがこのステップになります。
まずはギャンブル行動を引き起こす環境そのものを整えること。ギャンブル行動パターンに入らないように「近寄らない仕組み」や「気付ける仕掛け」を生活に組み込みます。
また日常生活でギャンブル以外の「ストレス対策」も行っていきます。
ギャンブル以外のことでも総合的な身の回りの環境を整えることで我慢に頼らない仕組みを作ることができ、ギャンブルをやめるためには我慢に頼るより現実的です。
STEP4では、「見える化」した行動パターンを元にギャンブルをしなくても良い環境を整えることを目指します。
ここからいくつかSTEP4の環境を整える方法についていくつか解説していきます。
詳細に関しては各個別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
①直接的なトリガーの対策
従来のギャンブル対策としてよく聞く、現金を持ち歩かない「行けないように物理的行動の遮断」は有効です。
ですがその効果の多くはギャンブル衝動が起きた後に効く、つまり行きたいけど行けないから我慢となり、我慢頼りになります。
そうではなく、その一歩手前“スイッチを入れないこと”に注目します。
- トリガー:きっかけ(お金、時間、場所など)
- スイッチ:きっかけが重なって入る(スイッチON=ギャンブル衝動)
ポイントは「トリガーを引かせない」ことで、脳のスイッチが入りそうな視覚・音・ルート・物品といった物理的なトリガーをあらかじめ排除・回避・遮断することで、“そもそも衝動が起きにくい環境”を作ります。
具体的には下記の物理的トリガーに対策を行います。
- スマホ・ネットからのトリガーを遮断
- 通勤・生活ルートを変える
- お金の使い方に“物理的ストッパー”をつける
- 視覚・感覚トリガーを物理的に消す
詳しい記事は下記をご覧ください
②関節的なトリガーの対策
上記に続いて間接的なトリガーに的をしぼって対策していきます。
具体的には下記の関節的トリガーに対策を行います。
- ギャンブル仲間など人間関係トリガー
- 落ち込んだときなど 感情トリガー
- 休日など時間・状況トリガー
詳しい記事は下記をご覧ください
③気持ちを整える「心のケア」の対策
ギャンブル依存症は様々な要因からギャンブルをやりたいという気持ちが高まります。
そしてその要因としてギャンブルとまったく関係なさそうな私生活でのストレスや健康維持が意外と大切だったりします。
脳が「快感を求めてブレーキが効かない状態」にならないために、日常の中でストレスを抜く仕組みを作っておく。
それがギャンブルをやめるために少しずつ効果を発揮してきます。
詳しい記事は下記をご覧ください
【STEP5】活動を習慣にして育てていく


STEP5では代替行動を習慣にして育てていくことがテーマです。
新しい行動を習慣にして育てていくことで“新しい回路を作ること”が目的になります。
たとえば、こんなふうに感じたことはありませんか?
- ギャンブルをやめたら絶対暇になる
- ギャンブルをやらない生活が想像できない
- やめたら何が面白いんだ?
その気持ちは、依存症の仕組みからすればごく自然なことなんです。
これは様々な研究で分かっていることですが、依存症になると
「脳がギャンブル以外のことに反応しにくくなる」といった変化が起こっています。
つまり、いきなり楽しいことを探そうとしても、そもそも脳が楽しめなくなっている状態なんですね。
だからこそ重要なのは、「楽しいかどうか」ではなく、
まずは“地味でも続けられる行動”を習慣にすることなんです。
3つの目的に分けて行動を設計する
代替行動といっても、目的は一つではありません。
このSTEPでは、以下の3つに分けて準備・実践していくことがポイントです
- 暇を埋める行動
→ 目的は「空白を作らない」こと。やめたあとの手持ち無沙汰を防ぎます。 - 衝動時の代替行動
→ 目的は「ギャンブル欲をそのまま別行動に流す」こと。気分の切り替えに使います。 - ブレーキとしての行動
→ 目的は「ギャンブルへのハードルを上げる」こと。行動を“遮断する仕組み”です。
そしてこれはギャンブルをやめるではなく他の物に置き換えるということ。依存行動をやめるには代わりになる行動をすることが効果的です
STEP5では「ギャンブルをやめてから代わりを探す」のではなく、
前もって生活に組み込んでおくことです。
継続していく中で少しずつ気づきが増え、
「意外とこの時間、落ち着くかも」
「やってみると、気分が整うな」
といった“小さな満足感”が生まれていきます。
そして最終的には、この新しい行動が育ち、
ギャンブルのポジションを押しのける存在になることを目指します。



機械では、回路を書き換える際に新しい回路を入れます。依存行動は回路が大量にあるようなものですので、少しずつ新しい回路を書き込んでいきます。
ここからいくつかSTEP5の新しい活動についていくつか解説していきます。
詳細に関しては各個別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
①まずは「空白」を埋める習慣化を目指す
ではどうするかというとギャンブルの代わりになるような楽しさを得るためにも、新しい活動を通して楽しさに気付くことが重要です。
そしてこの楽しさに気付く前にギャンブルに戻ってしまう、もしくはそもそもギャンブルを止められない場合がほとんどです。
ですのでやめた後からギャンブルで空く「空白」を埋める活動をしていくのではなく、ギャンブルをやめる前から新しい活動をして、まずは習慣にすることが第一目標になります。
詳しい記事は下記をご覧ください
②新しい活動の選び方
体を使う系やクリエイティブ系など様々な新しい活動になりえるものをリストにしましたので参考にしてください。
- ウォーキング(景色を見ながら)
- 筋トレ(軽い自重トレから)
- サイクリング
- イラストや落書き
- 音楽を聴く、楽器に触れる
- DIYやクラフト(100均DIY)
詳しい記事は下記をご覧ください
③習慣化はテクニック
重要なのは、新しい活動をただやるだけという楽しくなることをただ待つのではなく、自分から拾いに行く意識です。
やってみても続かないのは趣味になる為の小さな楽しみに気付いていないから。でもギャンブル依存症はギャンブル以外に興味が薄いことが様々な研究結果でわかっています。
ですのでまずは習慣化が先決。そのためのテクニックをいくつか紹介します。
仕組みの流れ
- まずは気付く
- やらない理由や邪魔を排除する(行動のハードルを下げる)
- 報酬を意識する(外発的報酬で習慣化)
- 既成事実を作る
- 「気づきポイント」を仕込む(報酬を増やす)
- 「記録」を用意する(できたことを可視化する)
詳しい記事は下記をご覧ください
【STEP6】依存衝動にルールを設ける


STEP6ではギャンブルをやりたい気持ちを下げていくことがテーマです。
依存の衝動にルールを設けることで衝動に逆らって一度止まり
“自分で選択できる回路を作る”ことが目的になります。
私たちは依存状態にあると、
「気づいたら行きたくなり、そのまま動き出していた」
と無意識に行動してしまいがちです。
このステップでは、“一度立ち止まる仕組み”=ルールを生活に取り入れていきます。
効果:3つの期待できる効果
ルールを作ることで得られる効果は大きく、次のようなものがあります
- 衝動をうまく使って、他の活動を促すエネルギー源にできる
- 衝動を感じたときに自動で行動せず、一度止まる習慣がつく
- 衝動にブレーキをかける“訓練”になる
具体例:やりたい気持ちを“ルール”に変える
たとえば、こんなルールを自分に設けてみます
「パチンコに行きたい。でも、その前に30分だけ散歩してからにしよう」
「衝動が来たら、まずは記録ノートに書いてから行く」
これは「行ってもいい」としているところがポイントです。
最初から“やめる”ことを目標にせず、
あくまで「○○をしてからならOK」というルールにすることで、
衝動と戦わずに自然と間を置けるようになります。
このルールを繰り返すことで、次第にこんな変化が起こっていきます
- ギャンブルを始めるまでに一手間かかる状態が当たり前になる
- 行動のハードルが高くなり、「まぁ今日はいいか」となりやすくなる
- 衝動を別行動のモチベーションに転換できる
なぜこの方法が効果的なのか?
ギャンブルはこれまで、「やりたいと思えばすぐにできる」「ほぼ無条件で手に入る快楽」でした。
しかし、“間にワンクッション挟む”ことで、脳にこう学習させることができます:
「これは簡単には手に入らない快楽だ」
「それなりに手間がかかるものだ」
この“ちょっと手間のかかる快楽”に脳が慣れていくことで、欲求の強さも徐々に落ち着いてくるのです。
ギャンブルは今まで、やりたいと思ったらすぐに手を出せる、苦労せずに手に入る快楽でした。それをこうして間に挟むことで、それなりに苦労しないと手に入らない快楽と脳が学習していきます。
STEP6では、このような「衝動にルールを設ける工夫」を繰り返しながら、
やがてギャンブルが「すぐに手を出すもの」ではなくなり、
気持ちのコントロールがしやすくなる土台をつくることを目指します。



たとえば私の場合、当初は「現金を持ち歩かない」といった方法を試していましたが、結局我慢できずにギャンブルに行ってしまっていました。でもこのステップで紹介したように、「行く前に筋トレをやる」というルールを試しました。最初にやったのは、本当にシンプルで、「行きたくなったらその場でスクワットをする」だけ。
ですがそれをきっかけに、少しずつ行動が広がっていきました。たとえば、公園を走ってみたり、ジムに行ってみたり。
こうしてギャンブルの前にやる“別の行動”が習慣になっていくうちに、
いつの間にか「ギャンブルには行かずに筋トレして、ついでに日用品の買い物をして帰る」というだけでも満足できる日が自然と生まれていました。
ここからいくつかSTEP6のルールについていくつか解説していきます。
詳細に関しては各個別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
①ブレーキは予め準備しておく
ギャンブルをやりたいと思った時に準備を始めていても間に合いません。なぜならその時点ですでに冷静さを失っているからです。
準備は冷静に判断できる平常時に行っておきます。
そうすることでブレーキをかける時は「こうすればよい」と考える必要なく、実行するだけで済むようになります。
基本的にはまず「体を止める」、次に「思考を止める」、次に「ブレーキを強化」、最後に「アクションに繋げる」という流れになります。
- ①:物理的に“ワンクッション” → 体を止める
- ②:思考を“遮断”する → 思考を止める
- ③:人やモノに“つながる” → ブレーキ強化
- ④:ユニークなブレーキ → アクション(別のことに集中)
- ⑤:ルールを設ける → アクション(別のことに集中)
何か1つではなく、流れが組めるように複数個パターンを用意しておくことが効果的です。
いきなりやめるのではなく、まずは自分で決めたこと、ルールを守ることがブレーキを強化することになります。そのためにもまずは一旦停止。ブレーキをかける練習から初めていきましょう。完全停止ではなく、一旦停止。
そのあとに進む道を自分で選ぶ練習になります。
詳しい記事は下記をご覧ください
②ギャンブル中に楽しまない工夫を織り込む
なぜやめたいのに行ってしまうのか?
それは
- ギャンブルは、勝ったときの快感を脳に強く学習させる
- 脳の報酬回路(ドーパミン系)が「もう一度!」と命令してしまう
- 思い出すだけで体が勝手に動いてしまう
これらの理由があります。
つまりギャンブルは楽しいと脳が学習している状態ということで、逆にギャンブルは「楽しくない」と脳に教えてあげれば依存を軽減できるということです。
そしてそのためには「刺激を弱める」ことになります。
パチンコ&スロットでは「レート」と呼ばれる貸出金額の設定があります。これを使って4円→1円に変えるなどが低刺激になるのですが、実際には上手くいかない場合が多いです。
その理由は4円の刺激が欲しくて耐えられないから。
この時、刺激が足りない部分を他の活動で補う準備をしておくことでフォローすることができます。
こうして徐々に低刺激に脳を慣れさせてギャンブルは楽しくない、けど他の活動があれば意外と大丈夫だと脳に学習させていけば徐々にギャンブルをやめていけます。
詳しい記事は下記をご覧ください
③ギャンブル行動前に決めた活動ルールを守る
内容としては、ギャンブルに行く際に事前に自分で決めた活動をしてから行って良いとルールを決めておき、それを実行するというものです。
「絶対に行くな!」ではなく「まず別の行動1回挟む」という作戦。脳は「行動パターンの順番」を変えるだけでも刺激の流れを修正できます。
まずはギャンブルを禁止するのではなく「条件付きでOKにする」ことがポイントです。
詳しい記事は下記をご覧ください
【STEP7】新しい生活サイクルを徐々に始める


STEP7では改善のサイクルを回すことがテーマです。
各ステップで準備したことを“生活に徐々に落とし込んでいく”ことが目的になります。
新しい行動を少しずつ繰り返すことで、脳の回路が書き換わり、ギャンブルへの欲求も徐々に減っていきます。
そしてそれを「やりっぱなし」ではなく、改善のサイクルとして振り返りながら継続することで、止まらずに進み続けられるようになります。
振り返りが“やる気”に変わる
・自分が変化したこと
・できるようになったこと
・今、やるべきこと
こうしたポイントを「やることリスト」などで確認しながら、小さな達成を実感していくと、それが自信や次のやる気につながります。
失敗しても“止まらない”ために
もちろん、うまくいかない日や失敗もあります。
でも、ここでは失敗を「やり直すチャンス」として捉え直すリカバリー方法も取り入れていきます。
活動が止まってしまわないように、失敗を前提にした現実的な仕組みを作っておくのも大切です。
たとえば、こんな変化が起きてきます
- 「今日はギャンブルに行きたいと思わなかった」
- 「毎日の散歩がちょっとした楽しみになってきた」
- 「ギャンブル以外でストレスを解消する方法が見つかった」
- 「気づけば月に数回しか行っていない」
このように、“気づけば行っていない”状態が、自然と生まれてくるようになります。
STEP7は「生活の改善サイクルを定着させる」ステップ
ギャンブルをやめることを目的にするのではなく、
やめても平気な生活スタイルを作っていくこと。
そのために、計画・行動・振り返り・改善の流れを習慣化して流れを作ることを目指します。



たとえば私自身も、最初は「またどうせ戻っちゃうんだろうな」と思っていました。
でも、毎週振り返ってみると、「先週より行きたい気持ちが少なかったな」とか、「代替行動は続いているな」といった、小さな変化に気づけたんです。
それが不思議と、自分への“肯定感”になっていきました。
「やっぱり変われるのかもしれない」って。
失敗ももちろんありましたが、「あの時はこうだった」と振り返って次に活かせるようにしていくと、逆に「止まらない仕組み」になっていたんです。
振り返ることで、ギャンブルから離れるだけでなく、自分のことも少しずつ信じられるようになっていきました。
ここからいくつかSTEP7の生活サイクルについていくつか解説していきます。
詳細に関しては各個別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
① 1週間単位で生活サイクルを回す
ギャンブルをやめるためにはギャンブルをやりたいと思わないように徐々にしていき、ギャンブルが必要ない生活にすることです。
そのためには様々な対策内容を生活に組み込んで馴染ませていけばおのずとなっていきます。
そしてそのサイクルを回す為の方法としてはPDCAサイクルと呼ばれる方法を使います。
とにかく行動が必要で、1日1日の積み重ねが大切。
ですので長期での計画ではなく、小まめに見直しが出来る1週間単位で生活サイクルを回すことがポイントです。
詳しい記事は下記をご覧ください
②振り返ることで「報酬」になる
なぜ振り返りが必要なのか?ですが、振り返りを通して
- 成果や達成感を自分で認識
- 脳に「報酬」として届ける
このように新しい行動回路を強化するエネルギーになります。
さらに、
「やってきたことは無駄じゃなかった」
「自分にもできるんだ」
という感覚が育ち、次のチャレンジ(完全にやめるステップ)へ向かう自信にもつながっていきます。逆に言えば振り返らないということは行動の意味、「報酬」を半分受け取らないようなもの。
せっかく行動をしているのですからその行動の報酬を受け取りましょう!
詳しい記事は下記をご覧ください
③リスト化して即実行できる仕組み
ギャンブルをやめるためには各場面において「行こうかな・どうしようかな?」と考えるのを阻止し、ふと行きたいとなった場合も「ブレーキ!」と考える暇を与えないようにすることが大切。
そのためにリスト化して仕組みにしておくことで、より簡単にギャンブルから離れることができます。
ギャンブルに対する知識を自分は持っているだろうか、休日の予定は埋めているだろうか、そういった準備が完了しているかどうかをチェックリストで確認してみましょう!
そして最終的には自分オリジナルのリストにして、見える化することで、自分にとってのギャンブルに対する最強の盾になっていきます。
詳しい記事は下記をご覧ください
④完璧を目指すと逆に続かない
失敗は駄目なこと、そんな風に考えていると「続けられない=ダメな自分」と考えてしまいがちです。失敗をしないとは裏を返せば完璧であるということで、些細な事すら失敗と捉えてしまうかもしれません。
「昨日までできていたのに、今日できない自分はダメだ」
でも現実として、途中でやめたくなったり、できない日があったりするのは人間なら当たり前です。そんな当たり前すら許さずに自分を責めると、脳はストレスを感じてしまい動きにくくなります。
そうではなく、
「失敗とは成長の糧になるチャンスである」
「現実的に考えたらそもそも失敗ですらなかった?!」
このように考えていけると目標に徐々に近づいていけます。
そしてその時にやるべきことは下記手順です。
- 【気付く】感情的になっていることに気付く
- 【冷静】判断は落ち着いてから
- 【観察】原因を客観的に見る
- 【現実】事実ベースで考える
- 【一歩】ルールをリセットする
- 【改善】環境などを変えて改善する
これは失敗をチャンスに変えて現実的に考えるリカバリー方法です。
日常生活のあらゆる場面で有効な手段ですのでぜひご活用ください。
詳しい記事は下記をご覧ください
【STEP8】実際にやめてみる


STEP8ではやめてみるチャレンジがテーマです。
まずは1週間だけ“ギャンブルから離れてみる”、そしてそれを繰り返すことが目的になります。
ギャンブル依存症の回復において、最終的には「ギャンブルをしない時間を作る」ことが必要不可欠です。
ただし、いきなりゼロにしようとしても、ほとんどの人はそこで挫折してしまいます。
そこで、STEP8ではこれまで積み上げてきた対策や習慣を活かしつつ、「実際にやめてみる経験」を小さく積み重ねることで、ギャンブルをやらないことへの抵抗感を下げていく段階になります。
これまでのSTEPで行ってきたこと
- ギャンブル衝動を起こさない環境や行動パターンの整備(STEP3〜4)
- ギャンブル以外の習慣や代替行動の育成(STEP5〜6)
- 新しい生活サイクルを整える仕組み(STEP7)
これらを通じて、「以前よりもギャンブル衝動が減ってきた」という人も多いはずです。
理想は、「もう週に何度も行かなくても大丈夫」という状態になっていること。
そこまで来たら、いよいよ「ゼロに挑戦するタイミング」です。
STEP8では、今までのSTEPで行ったことを維持継続しながら、さらにギャンブル衝動に対する対策を増やし、実際に行かないという選択をしてみる段階、衝動に負けない経験を積むことを目指します。



機械の本質は「絶対に壊れない設計」ではなく、「生産を維持継続していくこと」です。つまり故障は防ぐ方が良いが、その為にガチガチに対策して生活に支障が出たら本末転倒ということ。状況を見ながらあなたにあったチャレンジをしていきましょう!
ここからいくつかSTEP8の離れる方法についていくつか解説していきます。
詳細に関しては各個別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
①減少チャレンジをする
いきなりやめるのが難しい場合は、回数を減らす・1回の滞在時間を短くするといった「減らすチャレンジ」からでもOK。
これは「ゼロにするための準備運動」として有効で、負担を少なくして次のステップに進む土台を作ってくれます。
やり方
- 意識的に行かない日を作る
- ギャンブルの代わりになる代替行動を追加する
これだけです。
つまり「行きたいけど今日はやめてみよう」と意識的に行かない選択をして、代替行動をするということになります。
詳しい記事は下記をご覧ください
②禁止チャレンジをする
いきなり「一生やめる」と考えると重く感じてしまいます。
でも、「1週間だけ、試しにやめてみる」ならどうでしょうか?
これがSTEP8で目指す“ゼロチャレンジ”のスタートです。
- まずは「1週間だけゼロチャレンジ」
- 小さく成功体験を積む
- 無茶な我慢はしない
- 失敗しても「再チャレンジが前提」
- 自分を責めず、週末に「何が起きたか」を振り返って整理
1週間やってみて「いけそう」なら、また1週間
このやり方のいいところは、1週間ごとの区切りがあることです。
「ずっと我慢する」ではなく、
「1週間ならやれるかも」という“現実的なハードル”を設定することで、
無理なく続けられる形をつくります。
工夫は「続ける」ためにする
もちろん、毎週まったく同じやり方で継続できるとは限りません。
気持ちがきつくなってきたら、そこが工夫の入れどきです。
- 「なぜ今回つらかったのか?」
- 「何かできそうな対策はあるか?」
このように、やめる過程で必要になったら対策を追加していくのがポイントです。
必要なら「物理的なサポート」も使おう
1週間やめるチャレンジをするときに、
どうしても不安や衝動が強い場合は、
スマホ制限・財布管理・家族や支援者・入店制限サポートを受けることで入場禁止にするなど、
物理・精神的に“行けない環境”をつくる工夫も効果的です。
詳しい記事は下記をご覧ください
【STEP9】スリップしない心構え


STEP9ではスリップ対策(再発防止)がテーマです。
スリップしない、しても立ち直れる準備をすることで諦めずに進み続け、最終的にギャンブルを断ち切り、次の未来に進むことが目的になります。
スリップは再発、再燃など言われるギャンブルをやめて数か月後にまた何かがきっかけでギャンブルをしてしまうことを言います。
ここまでのステップを通して、ギャンブルから徐々に距離を置けるようになってきた方も多いと思います。
ですが、最後に大切なのが“スリップ対策”です。
STEP9では、「スリップしない」または「しても立ち直れる」仕組みをつくり、
諦めずに前に進み続けるための準備をしていきます。
最終的な目標は──ギャンブルを断ち切り、次の未来に進むことです。
ここからいくつかSTEP9のスリップについていくつか解説していきます。
詳細に関しては各個別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
① 1回でスリップはする!対策は心構えと生活サイクルを回すこと
かつての私は「1年やめられたし、もう大丈夫」と思って、たった1回だけ…とスリップしました。
すると、その1回が見事に崩壊の引き金になったのです(笑)
ですのでたった1回でもスリップはするということは、私が身をもって証明しました。だからこそ、みなさんには試さないでほしいんです。
スリップ対策の基本は「心構え」と「生活の維持」
ギャンブルに対する自分の防御力はゼロだと思ってください。
「1回だけなら…」という気の緩みが、依存を再起動させてしまいます。
そのための対策はシンプルです。
- 油断せず、日々の生活サイクルを守ること
- “良い依存”を支えにしておくこと
たとえば、こんな「良い依存」は強い味方になります
- チョコレートなどの甘いお菓子
- お笑い番組やYouTube、ゲームなどの気分転換
- 散歩や軽い運動
- 家族や友人、恋人との時間
「やらない」だけではなく、「他のことで満たす」ことがカギです。
もしスリップしてしまったら…
スリップはダメではありません。戻ればいいだけです。
その時はこうしましょう
- 自分を責めず、まず気持ちを整理する
- 「なにがあって再発したのか」を冷静に振り返る
- 必要ならSTEP4~7の対策を見直す
- そして、また一歩ずつ再スタートする
スリップは“終わり”ではありません。
次に活かすための経験です。
詳しい記事は下記をご覧ください
② 最終ステップ:ギャンブルを「断つ」という選択
このSTEP9のゴールは、ギャンブルを「禁止」ではなく、今後一生私はギャンブルをしないと決意して断つ、という覚悟を持つことです。
そう言える自分に近づくために、ここまでの準備を積み上げてきました。
ギャンブルのない世界を「辛い」と感じてしまうかもしれません。
でも、その先には──
- 時間に縛られない自由
- お金の不安がない生活
- 家族や仲間との信頼関係
こうした本当の安心感と自由な日常が待っています。
やり方
- 禁止」ではなく「不要」という意識を持つ
- もう必要ないからやらない、という前向きな決断。
- 平穏で退屈な日常を受け容れる
- 快楽を求めて退屈を嫌うのではなく、これが当たり前なんだと納得する。
- ギャンブルの無い世界で「何を得たいか」を明確にする
- やめた先に手に入る「自由」「安心」「時間」などをイメージする。
でも…ギャンブルだけが問題じゃないこともある
ギャンブルをやめると、別の問題が見えてくることもあります。
ギャンブルで狂った価値観、紛らわしていた孤独感、自己否定、過去のトラウマ。
それらがギャンブルに走る根本の原因だったりもします。
だからこそ、ギャンブルを手放した後こそが「本当のスタート」。
ギャンブルを忘れたら、次は自分の“本当の人生”に目を向けましょう。
今後の進め方
- ギャンブル以外にも問題があると受け容れる
- 自分を変えられるのは自分だけ
- 問題を受け容れて改善を続けていく
詳しい記事は下記をご覧ください
最後に:ここまで来たあなたへ
ここまで読み進め、取り組み続けたあなたは、本当にすごいです。
「依存症から抜け出す」というテーマは重く見えますが、
一歩一歩進めば、確実に未来は変わります。
スリップしない仕組みをつくりながら、
それでもダメなときは自分を責めずにやり直す。
この“強くて優しいループ”を、これからも回していきましょう。
関連記事
このサイトが大切にしていること
「この世界は、生きづらいものだ」と思っていた過去があります。
でも今は、そう感じていたのは“思考の回路”が乱れていただけだったんだと気づきました。
このサイト「ゆるやめ」では機械保全士として培った現実重視の“視点”をベースに、脳科学や心理学の知識そして私自身の体験を交えて、我慢ではなく緩やかな仕組みでやめるヒントをお届けしています。
よければ他の記事も覗いてみてくださいね。
参考・出典
- 厚生労働省,依存症についてもっと知りたい方へ,2025/4/21
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149274.html - 厚生労働省,依存症対策,2025/4/21
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.html - 厚生労働省「うつ病の認知療法・認知行動療法 患者さんのための資料」,2025/4/11
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/kokoro/dl/04.pdf