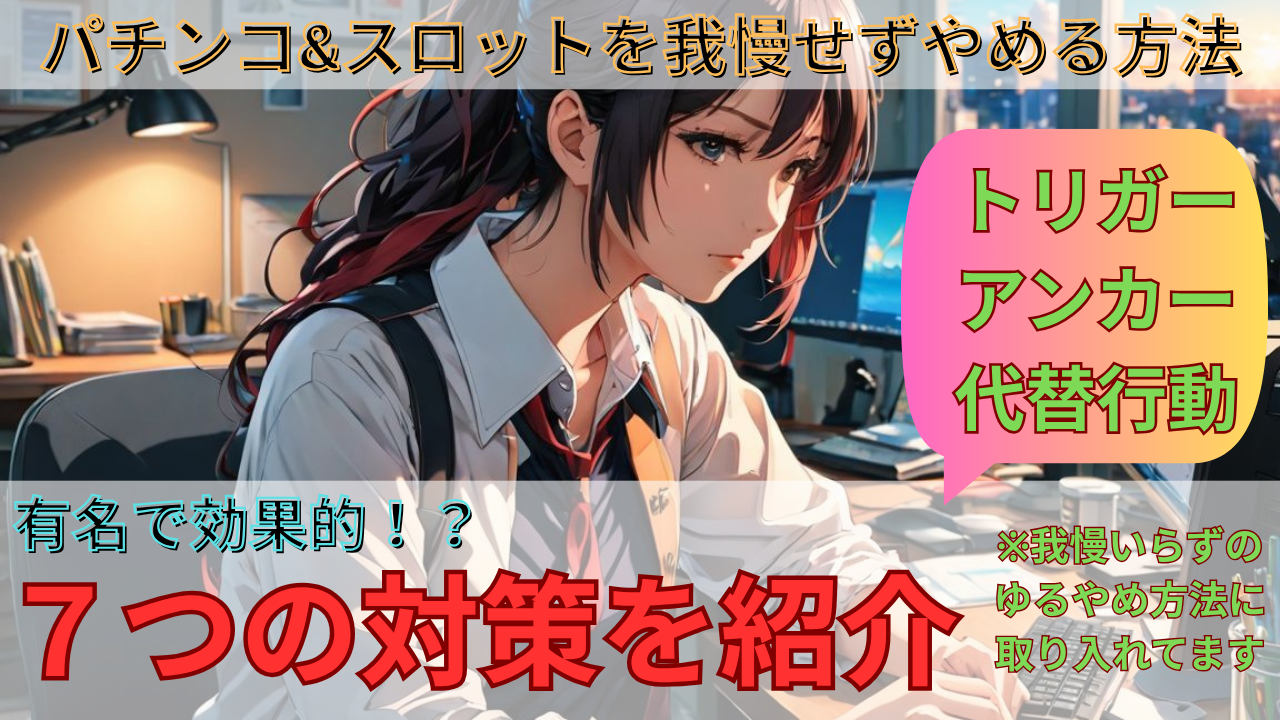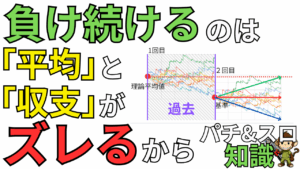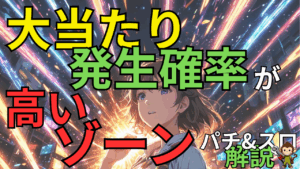パチンコ・スロットをやめたい方へ
こんにちは、「ゆるやめ」管理人のひろのぶです。
この記事では15年ギャンブル依存症だった私自身がパチンコ・スロットから抜け出した方法である、
我慢に頼らないでギャンブルをやめる方法「ゆるやか9ステップ」を解説しています。
この方法は…
「ギャンブルをやりながら」できる
「一人でも」できる
「気合に頼らず」できる
そんなギャンブルを論理的に仕組みを作って、ゆるやかにやめられる方法を知りたい方に向けて解説しております。
同じように悩んでいるあなたの、脱出の手助けになれたら幸いです。
- 「ゆるやか9ステップ」で取り入れている有効な対策はどんなものがあるか
- 依存症の要因(簡単に説明)
これらを知って頂くことで、9ステップでどんな効果があるのかをまずは理解してもらい、そのうえでステップの全体像の紹介へと進んでいきます。
【関連動画】

【説明1】一般的に効果があるとされる対策

一般的に効果があるとされている対策を7つ紹介していきます。
「ゆるやか9ステップ」では、これらの考え方や工夫を組み込んでいます。
【1】変化は少しずつ進める
私たち人は急な変化に強いストレスを感じやすい生き物です。
たとえば、ダイエットでいきなり「お菓子完全禁止!」と決めてしまうと、かえって反動がきてストレスが爆発し、リバウンドにつながりがちです。
でも、「お菓子を買い置きしない」「お皿を一回り小さいものに変える」など、環境を少し変える工夫や、
「階段を使うようにする」「週に1回、10分だけ散歩する」など、軽い行動の変化から始めると、無理なく続けやすくなります。
そして変化に慣れてくると、それが“当たり前”になっていき、さらに次の小さな変化も自然に受け入れられるようになります。
つまり、何かを始めるときは「一気に全部変えよう」とするのではなく、小さな変化を積み重ねていくことが成功のコツです。
【2】ノルマは逆効果
「絶対やめる」と決め毎日これをする!と意気込みすぎると、かえって反動でやる気が下がることがあります。これはノルマがあると「こなして当たり前」そしてノルマを下回ると「どんどんやる気が下がる」からです。
たとえば、ダイエットで「毎日1時間走る」とノルマを決めてしまうと、忙しかった日や体調が悪かった日にできなかっただけで、「もう無理だ…」とあきらめたくなります。
でも「できたら外に出るだけでもOK」としておけば、達成しやすく、逆に20分できた日は「思ったより頑張れた!」と自信になります。
人は自分の予想を上回るとやる気が出ます。
つまりやる気を上げるには低めに予想をして、ノルマは課さない。もしくは超えられるノルマであることが重要です。
【3】代替行動を用意する
依存行動の代わりになる行動をすることが効果的です。特に“同じような動作でできるもの”が有効とされています。これは脳が「頭の判断」だけでなく、「体の動き」とセットで記憶しているからです。
たとえば、毎晩ポテチを食べながらテレビを見る習慣がある人が、
「じゃあその時間はカット野菜スティックや素焼きナッツ」という代替行動に変えることで、
“手を動かす・口に入れる・くつろぐ”という体の動きは保ちつつ、お腹が膨れてリラックスできるという「満足感」を変えることができます。
こうして体を使った新しい習慣を繰り返すうちに、脳が「ポテチ=満足」ではなく、「別のものでも良い」と学び直してくれます。
【4】トリガーに気づき、関連する物を無くす、視界から消す
依存行動をしたくなる「直前の状況」──これがトリガーと呼ばれるきっかけです。
このトリガーに気づき、それを視界から消す・生活から外すことが、依存を遠ざけることに繋がります。
たとえばダイエット中なら、
「お菓子がいつもテーブルの上にある」
「夜コンビニに行くとついスイーツを買ってしまう」
「YouTubeで大食い動画を見たら急にお腹が空いてきた」
…これらがすべて“食べたくなるトリガー”です。
そこで、
・お菓子は家に置かない
・夜のコンビニには行かないルートを使う
・食べ物系の動画はおすすめから非表示にする
といった工夫で、
そもそも誘惑の元が近くにない環境をつくることで、自然と行動を変えることができます。
【5】トリガーと代替行動を組み合わせる
トリガーから依存行動をやりたくなった時、代替行動を間に挟むように組み合わせて行います。今まではトリガーから依存行動という脳の回路が出来てる状態でした。
たとえば「夜9時になると、ついアイスを食べてしまう」場合、これはすでに夜9時(トリガー)→ アイス(依存行動)という“脳の回路”ができている状態です。
この回路をそのまま断ち切ろうとすると、強い我慢が必要になって長続きしません。
そこで、夜9時(トリガー)→ ハーブティーを飲んでから読書(代替行動)といったように、間に別の行動を入れることで、脳が「夜9時=読書タイム」と覚えていき、脳の回路が書き換わっていきます。
最初は違和感があるかもしれませんが、繰り返すうちに脳はちゃんと覚えてくれます。
こうやって“やる行動”から“別のことをやる行動”に回路を少しずつ書き換えていく、「やらない」ではなく「別の何かをやる」のがポイントです。
【6】アンカー(宣言・外部要素)を活用
「誰かにやめるという」「自分を止めてほしい」など自分の周りの人に「宣言」します。こうすることで、その人達に「監視してもらえる」「もし行ったら自分の評価が下がってしまう」といった状況を作ることができます。
たとえば、あなたが「ダイエットする」と友人に宣言したとします。
その友人から「本当にそれでダイエットしてるの?」と聞かれることを想像すると…
“やらないと恥ずかしい”という気持ちが生まれますよね。
これはいわば、「自分を止めてくれるストッパー」を外に置いた状態。
この外部ストッパーが“アンカー”です。つまり、自分の行動を固定してくれる重り。
特にその相手が、信頼している人や応援してくれている人だと
「裏切りたくない」「ガッカリされたくない」という思いが強くなり、より効果的なブレーキになります。
ですのでよく依存症から抜け出すためにサポートが有効と言われるのは、この強力なアンカーになるからという点も大きいです。
【7】「行かない」と意識しない
ギャンブルを行かない、やめると意識していると、逆にギャンブルに意識が集中してしまいます。
これは心理的な現象で「カラーバス効果」とも呼ばれ、
「見ないようにしよう」と意識したものほど目につきやすくなるという仕組みです。
たとえばダイエット中に「甘いもの絶対食べない!」と決めると、
逆にケーキやお菓子がやたら目に入ってきて、余計に気になってしまう…
そんな経験はありませんか?
それと同じで、「行かない」と意識するのではなく、
「なぜ行きたくなるのか?」という“きっかけ”に目を向けて、対策を考える方が効果的です。
つまり、甘いものを避けるのではなく「お腹が空いたときに何を食べたくなるのか?」を考えておくように、
パチンコに行きたくなる瞬間や状況(トリガー)を見つけて対策をしていくのがポイントです。
 保全士:ひろのぶ
保全士:ひろのぶ私はギャンブル以外でもタバコをやめる際にこれら方法を取り入れてやめる事が出来ました。特にベイプと呼ばれる水蒸気が出るものを代替行動として行い、これが効果的だったなと感じています。
【説明2】依存症の要因


依存が続いてしまう要因を簡単に説明します。
依存が続いてしまう3つの要因
ギャンブルをやめられない理由は、主に次の3つです。
- 依存対象がある(いつでもギャンブルできる環境)
- 依存仲間がいる(同じような人たちと安心してしまう)
- 本人が“本心から”やめたいと思っていない
ダイエットでたとえると、家にいつでもお菓子やアイスがストックされている状態。
目に入ると、つい手が伸びてしまいますよね。これは「依存対象がある」に当たります。
次に「職場の休憩時間にみんなでお菓子を食べるのが習慣」だったり、
「夜にラーメンに付き合ってくれる友人がいる」など。
周りの人と“気を使わず楽しめる”環境ができていると、自分だけやめるのは難しいものです。これが「依存仲間」のような存在です。
最後に「本当は今のままでもいいと思ってる」
「ダイエットしろって言われるからやってるけど、別にやせたくない」
こんな状態だと、行動しても気持ちがついてこず、すぐに戻ってしまう。
これが一番やっかいで、外側(食べ物・仲間)を変えても、内側(本心)が変わっていないとリバウンドしてしまう原因になります。
このように、「環境+仲間+本心」
3つがそろって初めて、やめる準備が整います。
また、“本心”とはただの気持ちや意思だけではなく、「脳が学習して望んでいる状態」も含まれます。
つまり、「やめたいと思ってるのにやめられない」のは、あなたの意志が弱いからではなく、脳がまだその行動を“必要だ”と誤解しているだけなんです。
なお、この3つの要因について詳しく知りたい方は、別の記事で詳しく解説していますので、そちらもぜひご覧ください。
【まとめ】ポイントと一言


今回の内容のポイントは次になります。
ポイント:効果があるとされる対策7つ
- 一つ目、変化は少しずつ進める
- ポイントは何かを始めるときは、「一気に全部変えようと」とするのではなく、小さな変化を積み重ねていくことです。
- 二つ目は、ノルマは逆効果
- ポイントはやる気を上げるには低めに予想をしてノルマは課さないことです
- 三つ目は代替行動を用意する
- ポイントは「頭の判断」だけでなく「体の動き」とセットで記憶していることです
- 四つ目はトリガーに気づき、関連する物を無くす
- ポイントは誘惑の元が近くにない環境をつくることです
- 五つ目はトリガーと代替行動を組み合わせる
- ポイントは「やらない」ではなく「別の何かをやる」ことです
- 六つ目はアンカー(宣言・外部要素)を活用
- ポイントは信頼している人や応援してくれている人だとより強力なブレーキになることです
- 七つ目は行かないと意識しない
- ポイントは「行かない」と意識すると余計に気になるので「なぜ行きたくなるのか?」という“きっかけ”に目を向けて対策を考えることです
ポイント:依存が続いてしまう3つの要因
- 一つ目、依存対象がある(いつでもギャンブルできる環境)
- ポイントはやろうと思えばやれる範囲に対象があることです
- 二つ目、依存仲間がいる(同じような人たちと安心してしまう)
- ポイントは気の合う仲間から抜けて自分だけやめるのは難しい環境にいるということです
- 三つ目は、本人が本心からやめたいと思っていない
- ポイントは“本心”とはただの気持ちや意思だけではなく、脳がギャンブルは必要だと学習して望んでいる状態も含み、3つの要因の中で一番やっかいだということです。
最後に
今回紹介した方法はすべて、「我慢」や「気合」ではなく、“環境”と“仕組み”を使って対処する方法です。
こうした方法や他にもやめれる方法を取り入れてさらに具体的に何をすればよいか、どうすれば継続して活動ができるかと工夫を加えたものが「ゆるやか9ステップ」になっています。
次回
次回は「ゆるやか9ステップ」の目的と特徴について解説していきます。
続きはこちら
作成中です!
このサイトが大切にしていること
「この世界は、生きづらいものだ」と思っていた過去があります。
でも今は、そう感じていたのは“思考の回路”が乱れていただけだったんだと気づきました。
このサイト「ゆるやめ」では機械保全士として培った現実重視の“視点”をベースに、脳科学や心理学の知識そして私自身の体験を交えて、我慢ではなく緩やかな仕組みでやめるヒントをお届けしています。
よければ他の記事も覗いてみてくださいね。