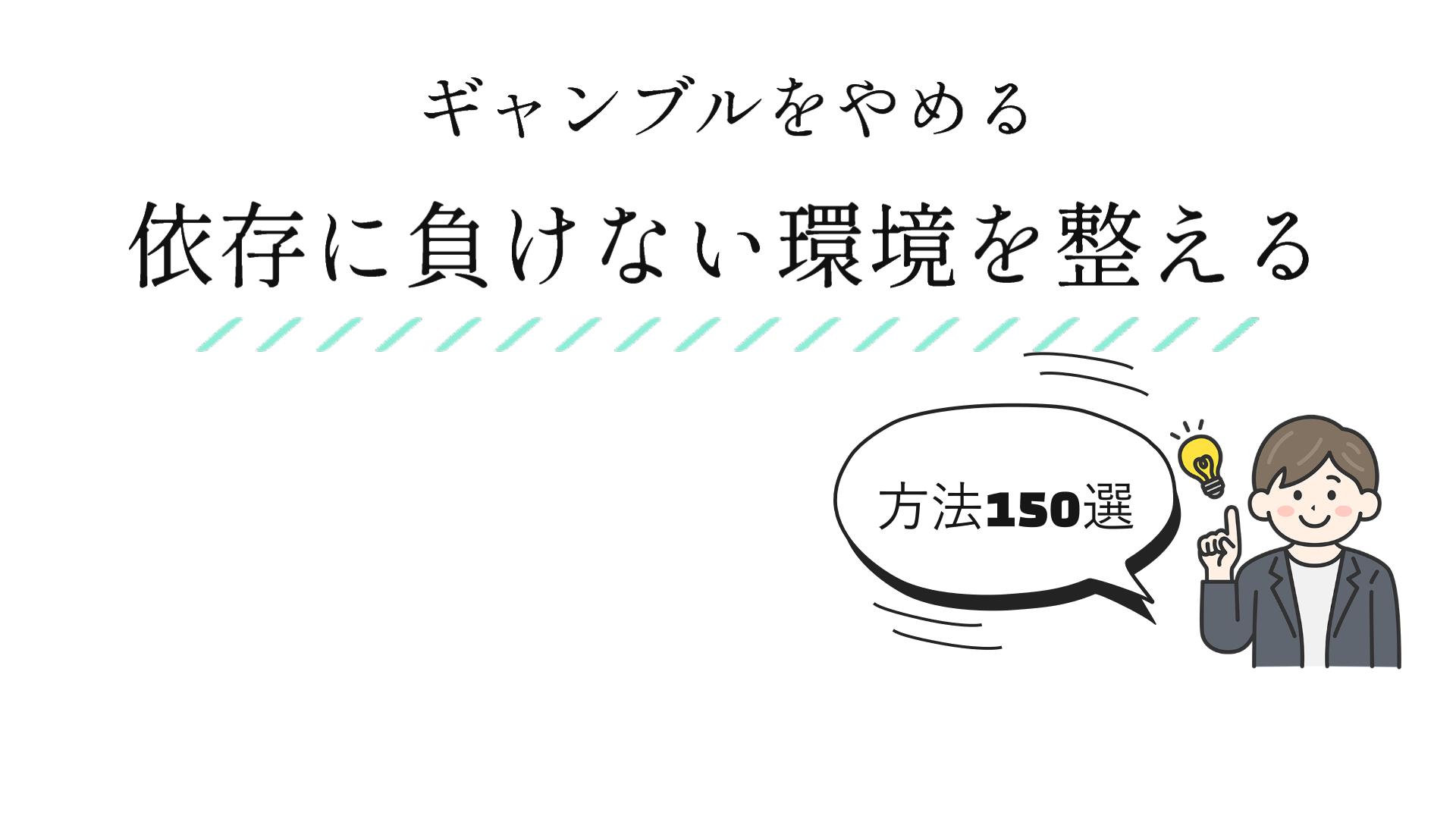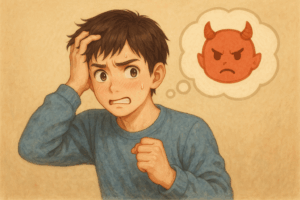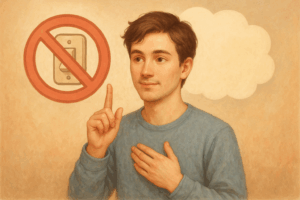環境を整えると「自分をコントロール」できる
こんにちは、「ゆるやめ」ブログです。
今回は、ギャンブルをやめるためのステップ4として、「依存に負けない環境を整える方法150選」という内容を解説します。
今回の内容を実施することで、ギャンブルに行きたくなる回数を減少させることができます。
前回のステップ3でみなさん自分の「トリガーとスイッチ」を知ることが出来たかなと思います。
今回はそのトリガーを引かないように自分の周りの環境を整えることで、スイッチが入る回数を減らしていきます。
でも具体的なやり方が分からないとそこで悩んでしまい、行動が止まってしまうと思います。
そこで今回は具体的方法として、僕が実際に行ったトリガー対策75選を参考にして頂ければと思います。
さらにトリガーだけではなく、ストレス対策方法も解説していきます。
なぜならストレスはそれ自体がトリガーになるだけではなく、ギャンブルをやめる活動の妨げにもなるからです。
今回の記事を読むことで、
- 【効果】ギャンブル衝動を減少させることができる
- 【方法】方法はトリガーを発動させない環境を整える
- 【メリット】この記事のメリットとして対策案75選・ストレス対策案75選を用意
- 【理由】ストレスはトリガーにもギャンブルをやめる活動の妨げにもなる
これらを活用して自分がどう対策をしていけば良いのかが分かります。
【関連動画】
記事と同様の内容が動画でも見られます。取り組みやすい方をお選びください。

【やり方①】トリガー対策「参考75選」
ここからはトリガーの対策方法を解説していきます。
対策の見方
まず記事の見方なのですが、
このトリガー対策方法は前回のSTEP3のトリガーチェックリストとリンクする形で作ってあります。
ですので、チェックした部分のみ見て頂き活用してもらうか、全体に目を通すかはお任せします。
最後に、先にポイントを1つ伝えておきます。対策はすべて「事前に行う」こと。トリガーが起こってから行うのではなく、起こる前に準備して予防・遮断します。
では解説していきます。
【実践①】「人]トリガー対策 17選
1つ目、【人】がトリガーになる対策としては次になります。
| トリガー | トリガーを引かせない工夫(予防・遮断) |
|---|---|
| ギャンブル仲間からのLINEや誘いが来ると行きたくなる | ● トーク通知をオフ・非表示にする/一時的にミュート・ブロックする ● 「返信を翌日にする」ルールを作り、即反応をやめる |
| 友人や職場の人とギャンブルの話題になった | ● 正直に自分はやめるから話題を振らないでとお願いする ● 話題を変える「ネタ」を準備しておく ● 友人や職場の人に会わない |
| SNSで誰かの勝った報告を見る | ● SNSのタイムラインをフィルター設定 or 特定ワードミュートする ● ギャンブル投稿が多い人のフォローを整理 or ミュートする ● 新規でアカウントを作成して状況を一変させる |
| ギャンブル好きの知人と会った後にやりたくなる | ● 次の予定で買い物・カフェなどを入れておく ● 知人にやめるから話題を振らないでとお願いする ● 知人に会わない |
| 職場でギャンブル好きの話を耳にする | ● 別の場所にいくなど物理的に距離を取る ● 休憩中はニュースを見る時間にするなど決めておく |
| 過去の思い出話や写真を見返してしまった | ● データをすべてPCに転送してスマホは空にする ● アルバムやデータを非表示・別フォルダ隔離 |
| 他人からギャンブル歴を話題にされたとき | ● 軽く笑って流す or「もうやってないよ」とポジティブに返すセリフを用意 ● 話題を変える「ネタ」を準備しておく |
【実践③】「時間・状況」トリガー対策 18選
2つ目、【時間・状況】がトリガーになる対策としては次になります。
| トリガー | トリガーを引かせない工夫(予防・遮断) |
|---|---|
| 給料日・ボーナス直後 | ● 自動振分け設定(貯金・生活費口座へ分散) ● 金額を確認しない、もしくは1回だけと決めておく ● 入ったらではなく事前に「買うもの」を決めておく |
| 平日休み・予定のない休日 | ● 「予定」(掃除・外出・映画鑑賞)を決めておく ● 「ノープラン=危険」と自覚しておく |
| お金に余裕があるとき | ● クレジットカード・QR決済などに切り替えておく ● キャッシュカード・通帳をしまう。(口座の金額を見ない工夫) |
| 特定の時間帯になると 「いつもの流れ」で行ってしまう | ● 予定を入れてアラームセットしておく ● 事前にその時間帯だけ |
| 家に帰る前に寄り道したくなる | ● 帰宅ルートを固定&別経路登録して意識的に迂回 ● 帰ったら好きな番組を見るなど予定しておく |
| 長時間移動中にスマホで検索する | ● 移動中は音楽・オーディオブックを聴く習慣に切り替える ● スマホのホーム画面を整理して誘惑するアプリを削除 |
| 季節イベントや特別な気分のとき | ● 旅行や気になっている店に行くなど予定を組み込む ● GWや年末年始は今までやったことが無いことにチャレンジする |
| 夜更かしして眠気があるとき | ● 夜はスマホ禁止 or 充電器を別室に置く ● 寝る前のルーティン(読書・ストレッチ・入浴)を固定化する |
| 月末や月初の金銭の節目 | ● 収支確認は「1日だけ」or「そもそも見ない」 ● 好きな漫画を買うなど決めておく |
「物理的」トリガー対策20選
【物理的刺激】がトリガーになる対策としては次になります。
| トリガー | トリガーを引かせない工夫(予防・遮断) |
|---|---|
| ギャンブル施設の前を通ると気になる | ● 通勤・移動ルートを変更 Google Mapなどで通らない経路を登録する。 経路をホーム画面に追加してワンクリックで表示できるようにしておく ●施設に向かう時使っていた道に近寄らない 施設ではなく向かう道がすでにトリガーの可能性がある |
| 昔勝った機種の名前や音、たばこの匂いを思い出す | ● 「連想させるもの」を避ける 動画サイトの登録削除 ホール近辺を通らない 喫煙所に近づかない ● アロマなど特定の香りで匂いを消す 車の芳香剤を変える ハンカチに香水をふり、匂う場合鼻に当てる |
| 過去の大勝ちがフラッシュバックする | ● 写真・記録・関連グッツなどを削除 |
| スマホやYouTube、SNSに ギャンブル系広告・動画が流れてくる | ● アプリの通知・広告表示をオフ、ブラウザの広告ブロック ● 「興味なし」と選択してアルゴリズムの調整 ● チャンネルを整理・非表示にする。 ● 新規でアカウントを作成して状況を一変させる ● アプリを削除する |
| ATMでお金を下ろすと衝動が起きる | ● 現金ではなくキャッシュレス決済に切り替える ● ATMでまとまった額を引き出さない (少額+目的別に封筒管理) |
| ギャンブルに使っていたノート・戦歴表など | ● 捨てる ● アプリ削除 |
| ギャンブル系アプリ・サイトがスマホにある | ● アンインストール ● アプリストアの制限設定(ペアレンタルロック) |
| コンビニ・駅の「当たる」系広告に引っ張られる | ● 行くコンビニを変更・限定・行かない選択をする (薬局に行くなど) ● 「買うもの」を店に入る前に決めておく ● 暇だから広告を見るので、代わりに本を読むなど決めておく |
| ギャンブルに使っていた財布やスマホケース | ● 物品の買い替え ● 旧グッズは処分 |
| ギャンブルシーンのある番組・アニメ | ● 番組を見れないように有料契約を解除 ● オススメされる媒体は登録解除 or 自動再生オフ |
| パチンコで使われていたアニメや曲を見聞きする | ● 自分からは見聞きしない (YouTubeで興味なし・チャンネルを非表示など) ● 見聞きした場合はすぐに切り替える |
| 部屋が静かで明かりも暗めな環境になると 過去のギャンブルを思い出す | ● スマホを別の部屋に置いて寝る/寝室でのスマホ禁止 ● 夜用の照明を「快眠モード」にし、環境そのものを“癒し空間”へ変更 |
【実践②】「感情」トリガー対策 20選
【感情】がトリガーになる対策としては次になります。
| トリガー | トリガーを引かせない工夫(予防・遮断) |
|---|---|
| ストレスで発散したくなる | ● 小さなケアとして深呼吸・温かい飲み物を飲むなどを小まめに行う ● ストレス日記(イライラを5行だけ書き出す)を習慣化する |
| 退屈・やることがないとき | ● 「気晴らし行動リスト」を作って予定を入れておく ● 動画鑑賞・散歩・気になる小説などの予定を入れておく |
| 孤独を感じるとき | ● 1日1回、誰かとLINEや通話するルーティンを入れる ● カフェ・図書館・ジムなど人の気配がある場所に定期的に行く |
| 落ち込んだとき気を紛らわせたくなる | ●「元気が出るリスト」(好きな音楽・動画・写真)を毎週更新する ● 温かい飲み物・シャワーなどの“物理リセット”行動を定期的に取る |
| 嬉しいことがあったとき浮かれる | ● 「気分がいい時する」リストを用意 ● 「幸せをおすそ分けする」リストを用意 |
| 不安や将来に焦るとき | ● 不安な気持ちを書き出して過去、現在、未来で分類して、「今やれる行動」をひとつ決める ● 誰かに相談する |
| 報われなかったとき取り返したくなる | ● 「勝ち負け思考に乗らない」「今日も前進」など自分に言い聞かせるワードを決めておく ● 定期的に気持ちは運動や掃除で発散する |
| 頭が疲れているとき刺激を求める | ●「疲れてる」とまずは自覚、リフレッシュリストを用意 ● 定期的に仮眠・甘いものを少し取るなど、そもそも疲れない工夫 |
| 自分を責めてヤケになるとき | ● 自己否定が出たら「書き出して可視化」して冷静に眺める ● ネガティブになったら誰かに短文LINEを送る |
| 他人と比べて落ち込むとき | ● SNSや他人との比較を遮断するため、「オフ時間」or「アプリ削除」する ● 過去の自分と今の自分を比べる「自己比較表」を作る |
ポイント
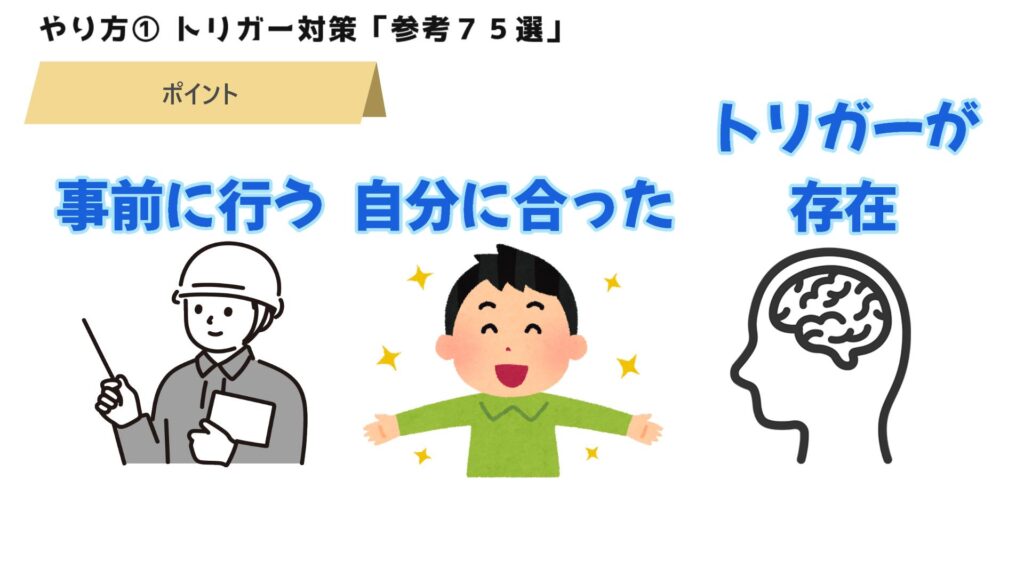
次はトリガー対策のポイントをいくつか解説します。
ポイント1つ目として、これら対策は「事前に行う」こと。トリガーが起こってから行うのではなく、起こる前に準備して予防・遮断しましょう。
ポイント2つ目として、対策は「自分に合った」方法を随時行うこと。今回の対策内容で完璧というわけではなく、あくまでも参考にして、自分に合った方法を行ってください。
ポイント3つ目として、行動にはすべて「欲求+条件+トリガー」があること。たとえば「お金が欲しい」欲求+「ギャンブルをするお金と時間がある」条件+「広告の誘惑や連想するもの」トリガー。これらがすべて整った時、行動の動機になります。ですので何かしら「行動にはトリガーが存在する」ので可能な限り対策していきましょう。
これらポイントを意識して対策を行うことで、我慢に頼らず、自然とギャンブルに行こうと思う回数が減少していきます。
トリガー対策としては以上となります。
体験談:動画について
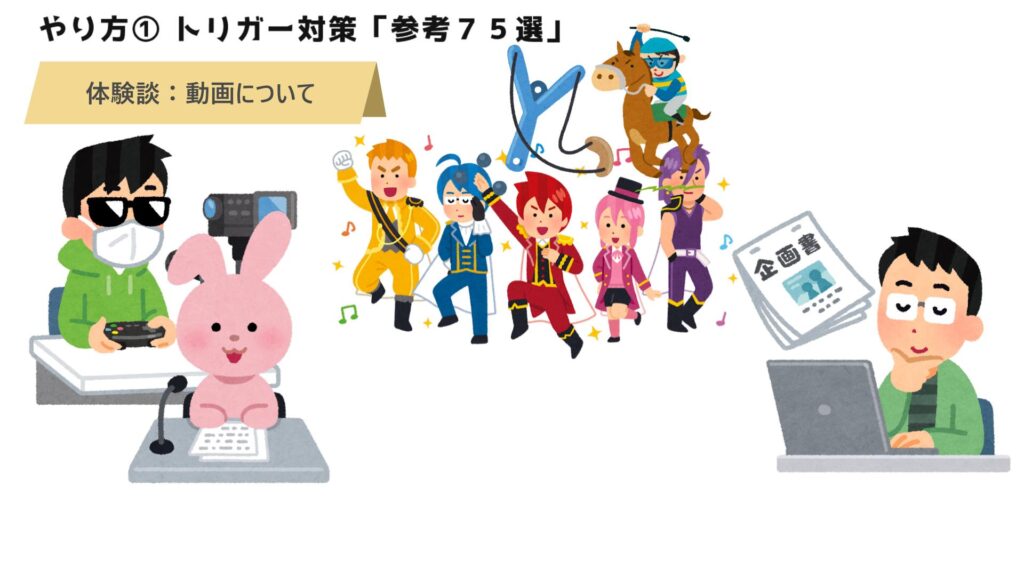
これは余談になりますが、最近トリガーで特に多いのがYouTubeと、YouTubeショートやティックトックなどショート動画だと思います。
なんとなく関連する動画を見始めてしまう。その後すぐ行こう、明日行こうという気になってしまう。これはまだ分かりやすいのですが、もう一つやっかいなことがあります。
それは全く関係ないジャンルの動画を見ていてもトリガーになりえるということ。たとえばゲームなどの実況動画や、ブイチューバーの動画です。
なぜかというとパチンコ・スロットはアニメと関係性が強いのでアニメの画像や曲、話題だけでトリガーになりえます。またパチンコやスロット、競馬企画の時もあります。これは、単純にアニメやギャンブル自体が人気コンテンツだから企画として行っているのでしょう。
ですのでその動画の人が好きだから見ているだけ、でもみなさんにその気が無くてもトリガーを見聞きしてしまうことがあるということです。
僕が今YouTubeでこの動画を出しておいて言いづらいのですが、このようなトリガーがみなさん自身にある場合は、そもそもYouTubeやティックトックのアプリを削除した方が良いかなと思います。
ただ、もちろんそれは嫌でしょうが安心してください。
僕もYouTubeやティックトックを全部消したことがあるので分かるのですが、いざ消してみると、無ければ無いなりの日常が待っています。これは好きな動画を見る時、まずはとりあえずアプリを開くというトリガーも消えているからです。
ですので思い切って削除すると本当に自然と見なくなります。
それにその好きな実況者の動画がまた見たいなら、それを励みにして頑張るのも一つの手です。受験勉強みたいなもので、終わってしまえばトリガーが多少あってもなんとかなります。
【理由】ストレス対策
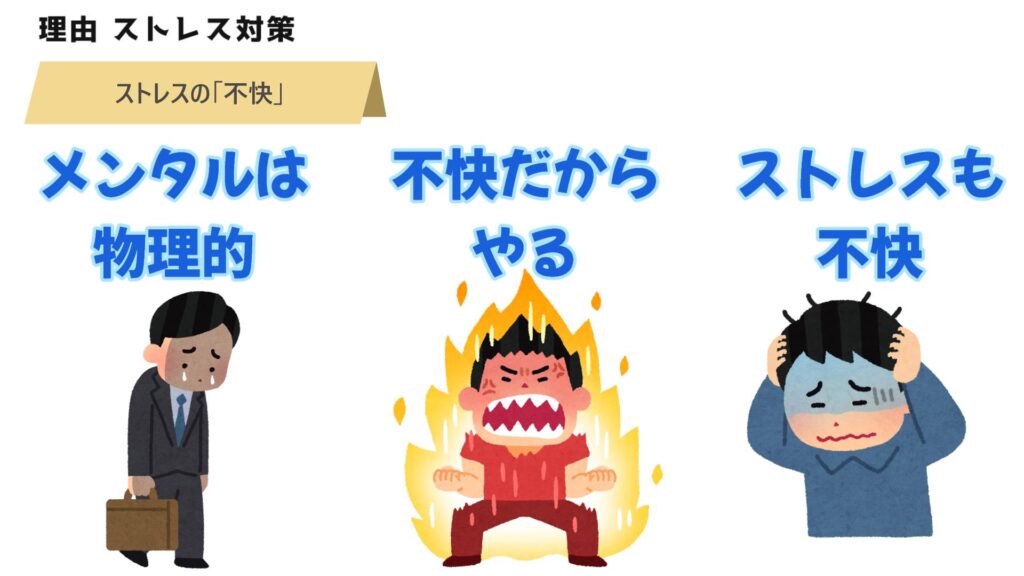
ここからはストレス対策の理由を解説します。
理由①:メンタルは物理的に整えられる
まず、ストレス対策や心のケアと聞くと、なんだか自分はメンタルが弱い人間なのかと思ってしまいがちですが、安心してください。
実はメンタルは脳の仕組みによるものです。ですので弱いというより、脳がそう感じてしまうような環境になっているだけかもしれません。
ですので環境を物理的に変えておくことでケアすることができます。
理由②:ギャンブルは「不快だから」やりたくなる
次にストレス対策がなぜギャンブルをやめることに繋がるのか簡単に解説します。
まず、多くの場合ギャンブルをやる理由が「不快だから」になります。これはギャンブルをやっていない時が不快だから、ギャンブルをやりたくなるという流れです。
理由③:ストレスの「不快」でもやりたくなる
ではギャンブルと全く関係ないストレスがあるとどうなるか。不快を解消できる手段としてギャンブルをすれば解消できると脳がすでに学習してしまっているので、ギャンブルに繋がりやすくなっています。
つまりどんな「不快」であってもギャンブルをする流れになりやすいということです。
それにプラスして、ギャンブルをやめる活動自体も環境が変わるので、不快と感じる場合があります。
ですのでストレス対策はギャンブルをやめる上で重要になってきます。
【やり方②】ストレス対策「参考75選」
ここからはストレス対策方法を解説します。
8種類ありますので順番に解説します。
① 朝の太陽光を浴びるルーティンを作る
まず1つ目は朝の太陽光を浴びるルーティンを作ることです。
太陽光を浴びることで不安感を和らげて精神を安定させることができます。これは脳のホルモン、セロトニンの分泌が促されるからです。
参考方法としては次になります。
- 深呼吸と瞑想(3〜5分)
- 朝日を浴びながらゆっくりと深い呼吸を行い、意識を“今ここ”に。心を整える。
- 軽いストレッチ
- 日光を浴びながら肩・腰・脚などをほぐす。血流促進&目覚め促進。
- 白湯または水を飲む
- 日光を浴びる直前・直後にコップ1杯の水分補給で内臓も起こす。
- グリーンを見る or 植物に水やり
- 朝の光を浴びながら植物に触れると、癒し&自然とのつながりを感じられる。
- 日光浴しながら日記を書く
- 朝の気持ちや目標、感謝などを書き出す「モーニングページ」習慣。
他にもこんな“朝ルーティン”があります
- ウォーキング(外で15〜30分)
- 朝の光を全身で浴びながらの散歩は体内時計リセットにも効果大。
- ベランダでラジオ体操
- 短時間で全身を動かせる万能な軽運動。朝日+リズム運動が爽快。
- ポジティブな言葉を声に出す(アファメーション)
- 「今日も元気」「自分らしく」など前向きな言葉を繰り返す。
- 太陽礼拝(ヨガ)
- 朝に最適なヨガの動き。全身を気持ちよく動かし、代謝アップ。
- 姿勢を整えて静かに立つ(立禅)
- 朝日を浴びながら目を閉じてゆっくり立ち、身体感覚に集中するマインドフルネスな習慣。
ちなみに僕はカーテンを開けて歯を磨きながら朝日を浴びる、朝食後にかるくストレッチしながら浴びるルーティンにしています。気が乗らない時は白湯飲みながらぼけっと浴びてるときもあります。
② 軽く体を動かす
2つ目は軽く体を動かすことです。
運動には二つの効果があり、一つ目は軽い運動をすることでリラックスできます。これは脳のホルモン、セロトニンやエンドルフィンの分泌が促されるからです。
参考方法としては次になります。
- ウォーキング
- ゆっくりとしたペースでの歩行(1日20〜30分が目安)
- ストレッチ
- 筋肉をほぐす柔軟運動(全身 or 部位ごと)
- ラジオ体操
- 全身を使った軽い運動(約3〜5分)
- 軽い階段昇降
- 1段ずつゆっくり昇り降り(心拍数も軽く上がる)
- ヨガ(入門レベル)
- 呼吸と連動したポーズで柔軟性と心の安定を向上
他にもこんな“軽い運動”があります
- 太極拳
- ゆっくりとした動きで全身を使うバランス運動
- 椅子を使ったスクワット
- 椅子を使って浅めのスクワット(膝に優しい)
- 足踏み運動(室内)
- その場で行う足踏み(テレビを見ながらでも可能)
- バランスボール座り
- 姿勢を保ちながら体幹を軽く鍛える
- 肩回し・首回し
- 仕事の合間にもできる上半身のほぐし運動
負荷の高い運動
二つ目は負荷をかけた運動をすることでストレスに強くなっていきます。これはホルモン、コルチゾールの分泌バランスが整うからです。
参考方法としては次になります。
- ランニング
- 心肺機能向上に効果的。距離・時間を決めて継続
- HIIT(高強度インターバルトレーニング)
- 短時間で高強度を繰り返すトレーニング(例:タバタ式)
- 腕立て伏せ
- 上半身の筋力強化に。フォーム重視
- スクワット(加重あり)
- ダンベルやバーベルで負荷を加える。下半身全体に効果的
- 自転車(速いペースまたは坂道)
- 有酸素と筋力の両方に効く運動
- 縄跳び
- 持久力とリズム感が鍛えられる全身運動
- 登山・ハイキング(中〜高難度)
- 負荷が高く、長時間の持続で脂肪燃焼も◎
- プランク(長時間)
- 体幹を強化する静的な筋トレ。60秒以上キープなど
- ジャンピングスクワット
- 爆発力と下半身強化に。スクワットより高強度
- 懸垂(チンニング)
- 背中・腕・体幹を鍛える高難度トレーニング
ですので、まずは軽い運動から初めて、運動に慣れてきたら負荷をかけた運動も取り入れると、ストレスを減らし、さらにストレスに強くなります。
③ 不安やイライラは書き出す
3つ目は不安やイライラは書き出すことです。
感情を紙に書くだけで、モヤモヤが少し晴れます。これは脳科学的に脳の前頭前野と呼ばれる脳のブレーキが活性化してコントロールしやすくなるからです。
参考方法としては次になります。
- 何があったのか事実だけ書く
- そのときどう感じたかをそのまま書く
- 過去・現在・未来で分類してみる
- 手書きが面倒ならスマホメモでもOK
- 誰にも見せない前提で書く
他にもこんな“書き方の工夫”があります
- 「今不安なことTOP3」を書く
- 「こうなったらいいのに」願望を妄想してみる
- ネガティブなことの裏にある“望み”を見つける
- 終わりに一言「おつかれ」と自分に書く
- 過去・未来の自分へ手紙を書く気持ちで書く
補足ですが信頼できる相手に悩みを話すだけでもストレスは大きく低減されます。
④ 1日1つ安心スイッチを用意する
4つ目は1日1つ安心スイッチを用意することです。
自分が安心できる行動や空間にいることで、リラックスできます。これは脳のホルモン、セロトニンやオキシトシンの分泌が促されるからです。
参考方法としては次になります。
- パートナーや家族とハグや会話
- 会話や抱きしめ合うことで安心感が生まれる
- ペットをなでる/ぬいぐるみを抱く
- 抱きしめることでも安心感が生まれる
- ぬるめの入浴(38〜40℃、15分以内)
- 身体を温めてから徐々に冷やすと、眠気を誘いやすくなる。
- 本を読む(紙がおすすめ)
- 心を静めるジャンルで、感情を落ち着ける。
- アロマを焚く(精油やスプレー)
- ラベンダー、ベルガモット、カモミールなどが安眠に効果的。
- ハーブティーを飲む
- カフェインレスのカモミールティーやルイボスティーで心を静める。
- スマホ・PCを消して“照明を落とす”
- ブルーライトを避けて暗さに慣れると、メラトニン(睡眠ホルモン)が分泌されやすくなる。
他にもこんな“安心スイッチ”があります
- 今日の感謝や出来事を書き出す
- ポジティブな記録で心を穏やかに整える。
- クラシックやヒーリング音楽を流す
- 自律神経を整える1/fゆらぎの音楽や自然音も効果的。
- 深呼吸・腹式呼吸
- ゆっくりとした呼吸で副交感神経を優位に。心拍や思考が自然に落ち着く。
- 軽いストレッチやヨガ
- ベッド横や布団の上でできる柔らかい動きで、身体のこわばりを緩める。
- 瞑想やマインドフルネス(5〜10分)
- 思考を手放し、“いま”の感覚に集中することで入眠しやすくなる。
注意点として、お酒や食べ過ぎ、スマホいじりはリラックスのつもりでも実際には休まりません。
また可能なら月に1回でも良いので自然に触れれるキャンプなどおすすめです。
⑤ SNSやニュースから距離をとる
5つ目はSNSやニュースから距離をとることです。
距離をとることで、脳の疲労を防ぐことができます。これはSNSやニュースからの刺激は情報過多となるからで、脳は見聞きしたことを無意識に処理しようとして疲労してしまいます。
参考方法としては次になります。
- 通知をオフにする
- SNSアプリを1回アンインストールしてみる
- ニュースを見る時間帯を決める(例:昼だけ)
- フォロー・登録を整理する
- 「1日SNSを見ない日」をつくってみる
他にもこんな“情報デトックス術”があります
- スマホの「集中モード」を活用する
- 寝る1時間前にスマホを手の届かない場所に置く
- スクリーンタイムを見て使用時間を把握
- YouTubeのおすすめを無視して目的の動画だけ観る
- スマホを「タイムロッキングコンテナ」にいれる
⑥ 日々の作業を効率化して無駄な判断を減らす
6つ目は効率化して無駄な判断を減らすことです。
判断を減らすことで脳の疲労を防ぐことができます。これは意思決定を重ねることで脳のエネルギーを消耗してしまうからで、パフォーマンスが低下していきます。
参考方法としては次になります。
- 毎朝やることリストを固定化(朝の3ステップ)
- “服・食事・道”などを1パターンにして選ばない
- 日用品のストックは“2個ルール”に統一
- 1日1回、時間を決めて“まとめ対応”をする(メール、買い物など)
- 手帳やGoogleカレンダーに「予定の型」を作る
他にもこんな“効率化方法”があります
- 買い物リストは定型フォーマット化(毎週コピペ)
- ToDoリストに“やらないことリスト”も併記する
- 音声入力 or チャットでメモを取る
- 寝る前に「明日やらないこと」を1つ決めておく
- 「やる→記録→振り返り」の3ステップをルール化
⑦ 脳をトレーニングしてリフレッシュ&強化する
7つ目は脳をトレーニングすることです。
トレーニングすることで脳のリフレッシュと強化ができます。
脳は「慣れていないこと」、「新しいこと」、「ちょっと考えること」といった小さな刺激や考える負荷を与えることでリフレッシュしたり、機能が向上したりします。
参考方法としては次になります。
- 脳トレアプリ
- 数独・計算・間違い探しなど
- 逆利き手で日常動作
- 歯磨き・箸
- 短時間の集中ゲーム
- テトリス、ミミズゲームなど
- 新しい道を歩く・乗る
- 1日1個、何かを暗記する
- 名言、英単語
他にもこんな“トレーニング方法”があります
- 今日の出来事を「3行」で要約する
- 新しいレシピに挑戦する
- 軽い筋トレやストレッチをしながら逆算で数字を数える
- 人と雑談する(できれば初対面の人と)
- 1日1つ「なぜ?」を考える習慣
⑧ 栄養を整えて心をサポートする
8つ目は栄養を整えて、心をサポートすることです。
栄養をしっかりとると、心が安定しやすくなります。
これは私たちの心、精神、メンタルは、気合や気分だけで決まるわけではないからです。ここまで解説で出てきたセロトニンなど「ホルモン」の影響で変わってきます。そしてこのホルモンは、食事から摂る栄養素を材料に作られていることが知られています。
ですので栄養が不足していると、どんなに頑張っても心は安定しにくくなります。
特に意識したい栄養素
- たんぱく質(セロトニン・ドーパミンの材料)
- ビタミンB群(セロトニンを作り出す為にビタミンB6が必要)
- 鉄・亜鉛・マグネシウム(神経伝達の正常化に関与)
参考方法としては次になります。
こんな工夫をしてみよう
- 朝食に「たんぱく質」(卵・納豆・ヨーグルトなど)を少しでも入れる
- できる範囲でバランスの良い食事を意識
- 食事だけで難しければマルチビタミンやプロテイン補助も一つの手
- 無理なダイエットや偏った食生活を避ける(極端な糖質制限なども注意)
- 間食として「ナッツ」を食べる
ホルモンの材料としてたんぱく質とビタミンB群を摂取しておけば大体補えそうです。あと鉄、亜鉛、マグネシウムも脳の神経伝達に影響があるとされています。
ポイント

ここからはストレス対策のポイントを解説します。
ポイント1つ目として、ストレスなどメンタルは「物理的に対策が可能である」こと。気合や根性ではなく、脳の仕組みです。ですので朝日を浴びる、健康的な食事など物理的な対策が有効になります。
ポイント2つ目として、ストレスは「発生させない、溜まる量を減らす、溢れる前に解消する」の順番で対策すること。単純ですが発生しなければ解消の必要は無くなります。
今回のストレス対策は簡単なものをピックアップしてみました。こうした方法があると知ることで他にも応用ができるかと思います。
ストレス対策としては以上となります。
【今回のまとめ】
それでは今回のまとめになります。
【テーマ】
STEP4のテーマは、依存に負けない環境を整えることになります。
目的として、STEP3で見えてきた自分の行動パターンをもとに、「どうすればギャンブルに繋がらないか?」を仕組みとして生活に組み込んでいくことになります。
またストレス対策方法も環境を整える方法ということで一緒に解説しました。
【内容】
今回の内容としては次になります。
- トリガー対策では、
- 次の4つ、人、時間や状況、物理的刺激、感情に対するトリガー対策を解説
- ポイント1つ目として、これら対策は「事前に行う」こと。
- ポイント2つ目として、対策は「自分に合った」方法を随時行うこと。
- ポイント3つ目として、行動には「すべてトリガー」があること。
- ストレス対策では、
- 次の8つ、朝の行動、運動、書き出す、安心スイッチ、SNSから距離をとる、作業効率化、脳トレ、栄養に関するストレス対策を解説
- ポイント1つ目として、ストレスなどメンタルは「物理的に対策が可能である」こと。
- ポイント2つ目として、ストレスは「発生させない、溜まる量を減らす、溢れる前に解消する」の順番で対策すること。
内容としては以上になります。
最後に一言:他にも様々な知識がある
最後に、今回のステップから自分の環境を整えるという「変化」が生まれます。人は変化を嫌う生き物ですので、少しずつ自分のペースでゆるやかに進めていきましょう。
また人は「不安」も嫌います。今回の記事が何をやったらいいか分からないといった「不安」を無くすお役に立っていれば幸いです。
それでは今後もこのような記事を投稿していきますので、いいなと思ったらブックマークしてくれると嬉しいです。
最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう。
関連記事
備考
このサイトが大切にしていること
「この世界は、生きづらいものだ」と思っていた過去があります。
でも今は、そう感じていたのは“思考の回路”が乱れていただけだったんだと気づきました。
このサイト「ゆるやめ」では機械保全士として培った現実重視の“視点”をベースに、脳科学や心理学の知識そして私自身の体験を交えて、我慢ではなく緩やかな仕組みでやめるヒントをお届けしています。
よければ他の記事も覗いてみてくださいね。
参考・出典
- 厚生労働省,依存症についてもっと知りたい方へ,2025/4/21
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149274.html - 厚生労働省,依存症対策,2025/4/21
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.html