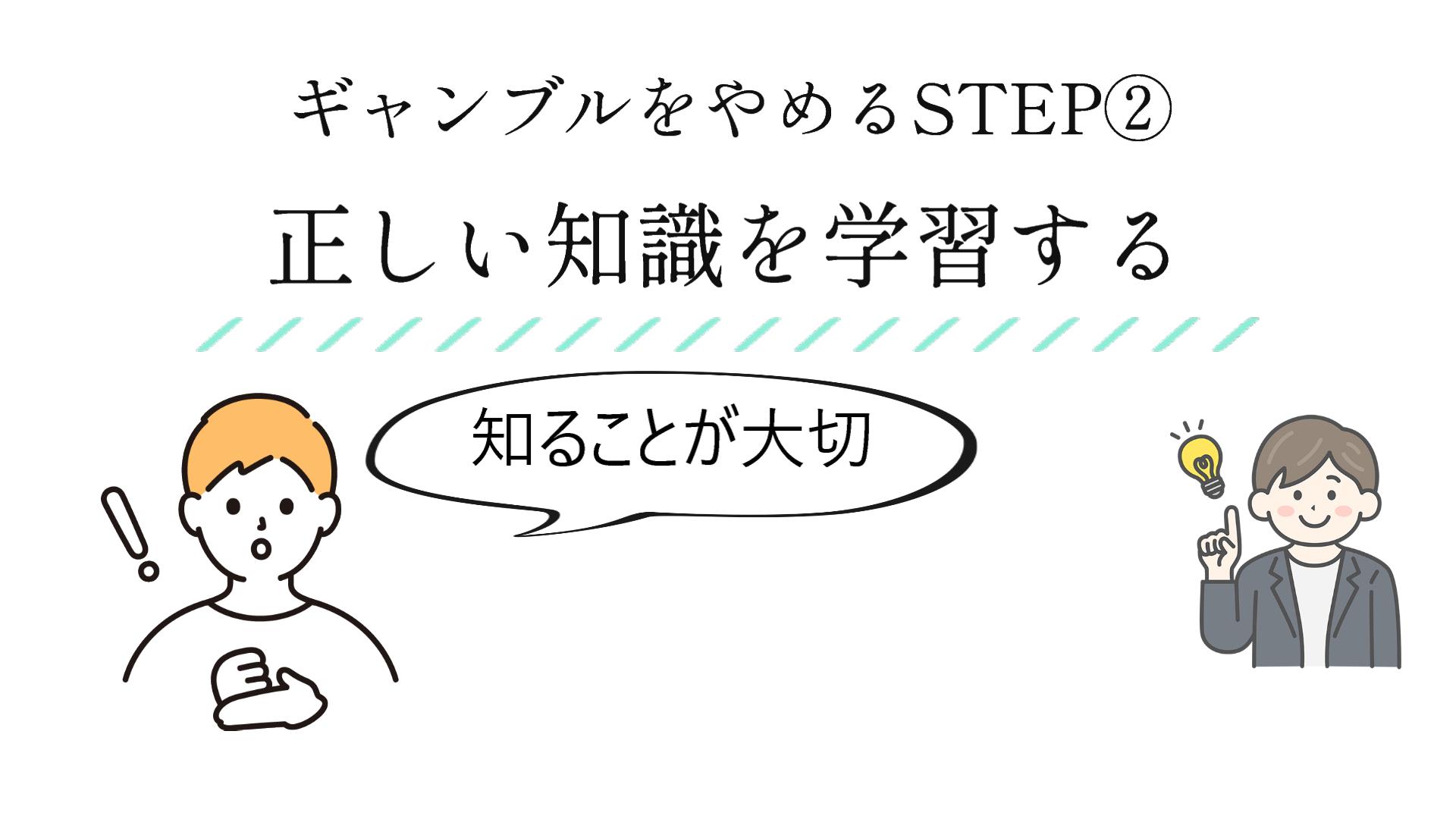知識を得ること自体が気持ちを抑えることに繋がる
こんにちは、「ゆるやめ」ブログです。
今回は、ギャンブルをやめるためのステップ2として、正しい知識を学習する。という内容を解説します。
たとえば、「自分は意志が弱いのかもしれない…」
このような“否定”を防ぐことができます。また努力や行動の方向性を修正して、我慢に頼る“悪循環”を止めることができます。
そしてここが今回のポイントで、知識を学習すること自体が、ギャンブルをやりたい気持ちを抑えるというメリットがあります。
今回の記事を読むことで、どのような知識が必要なのか。そしてどのような効果があるのかが分かります。
ちなみに今回は、知識をまとめた内容になっていますので、他の動画と内容が重複することがあります。
【関連動画】
記事と同様の内容が動画でも見られます。取り組みやすい方をお選びください。

【知識①】依存と依存症の違い

まずは、「依存」と「依存症」の違いについて解説します。
「依存」ってどんな状態?
簡単に言うと、「依存」はその対象を頼りに生活している状態のことをいいます。
でも、「やめよう」と思えば自分の意思でやめられる。
ここが「依存症」との一番大きな違いです。
では「ギャンブル依存症」って何?
では、ギャンブル依存症はどうかというと
これは、ドーパミンによる快楽を“異常に”求めるようになった状態です。
つまり、やめたくても脳がやめたいと思っていないから、やめられない。
これが「依存症」の状態です。
【知識②】依存の3つの要因

次に、依存や依存症になる要因について解説します。
簡単に言うと要因は3つあり、1つ、依存対象があること。2つ、依存仲間がいること。3つ、本人がやめたいと思わないことです。
この3つに対して対処することで、ギャンブル依存症は抜け出すことができます。
1つ目は依存対象であるパチンコ、スロットが自分の手の届く範囲にあることです。これは分かりやすいですが対象がなければ依存も出来ませんし、どんなにやりたくなってもやれません。
2つ目は依存仲間がいることです。これは本人の周りに同じくギャンブルをやっている人がいることを指しています。自分が仲間と認識できる対象がいることで孤独感や罪悪感が薄れていきます。だから仲間がいると依存が強まる。
3つ目は本人がやめたいと思わないことで、依存症からの脱出は本人の意志が一番大切になってきます。ただここでややこしいのが、やめたいと考えている本人と、心や脳の思いは別物だということです。
詳しくは次で解説していきます。
【知識③】脳の3つの役割

次に、脳が持つ3つの役割について解説します。
- 1つ目は、【頭】、私たちが意識して考える、【理性】。
- 2つ目は、【心】、脳が行う無意識、ギャンブルをやりたいと思う【感情】。
- 3つ目は、【体】、脳が行う無意識、不快を取り除く、食べたいものを食べる、一番強くギャンブルをやりたいと望む、【生存本能】。
この3つになります。
力関係が存在する

ここでやっかいなのが、力関係が存在することです。
【理性】が一番弱く、【感情】が中間、【生存本能】 が一番強いという力関係があります。
だからよく、意思の力でギャンブルはやめられないと言われるのは、この力関係で負けているからになります。
意識と無意識が存在する

そして意識的と、無意識的。この活動する割合は様々な研究から分かっており、
- 意識的な思考は10%、
- 無意識的な思考は90%
となります。
つまり人はほとんど無意識的に考えて行動しているということになります。
結論:私たちの意思と、脳の判断は違う。
これがポイントで、私たちの意思と、無意識に行われる脳の判断は違うということ。そして無意識の方が力が強い。ですのでギャンブルから抜け出すためには、この無意識の脳をなんとかしなければいけません。ちなみにこれは僕の場合ですが、自分の脳を、自動で動く別の物と捉えた方が今後扱いやすくなります。
【知識④】ギャンブルと脳の学習

次は、ギャンブルと脳の学習について解説します。
脳が「快感」を強く学習する
ギャンブル依存の最初の一歩は、脳が「快感」を強く学習してしまうことです。
たとえば
「楽しかった」
「気持ちよかった」
「ストレス発散になった」
このような体験をすることで、ギャンブルは快楽が味わえると脳が学習します。
この学習の結果、脳が無意識に“期待”する“スイッチが入り”私たちは無意識にやりたい気持ちになって、行ってしまうという行動に移ります。
ドーパミンの役割
この時、ドーパミンと呼ばれる脳の神経伝達物質の一つが分泌されています。
報酬系回路
このドーパミンが報酬系回路と呼ばれる回路と結合することで、「快感」や「意欲」などの「感情」が引き起こされます。
予想することで分泌される
そしてこのドーパミンは快感で分泌されるわけではなく、予想した時や予想と違う場合に分泌されるとされています。
これは、「行動すればこうなるはず」と予想、つまりシミュレーションしている状態です。
だからギャンブルに関係するものを見たりすると、脳が勝手に予想して、行きたくてウズウズしてしまうことになります。
ドーパミンの多量分泌は意外性

そしてこの予測に誤差がある、つまり意外性、予想より大きな報酬があるとより多くのドーパミンが分泌されます。
ギャンブルで、「やってみたら意外と面白い」、「思ったより連チャンして嬉しい」などがこれです。
だから世の中では、意外性があるものが、この予想を上回り、新鮮で、楽しいと感じ、より記憶に残りやすいことになります。
脳の回路が強化されていく

こうしてドーパミンの分泌を繰り返すことで、徐々に脳の回路が「強化」されていきます。
イメージとしては車が走る道路で、最初は1車線だった道路、でも交通量が増してくると2車線へ、さらにどんどん増えて3,4車線へと変わっていくようなもので、この交通量がドーパミン、車線数が脳の結合です。こうして脳にとってこの道は重要だと判断されて強く、太くなっていくことになります。
結論:「やるか、やらないか」で学習は変わる
ここがポイントで、逆にやらなければ重要ではないと、「弱く」なっていくので、「やるか、やらないか」で学習は変わります。
だからギャンブル依存症は少しでも「やらないことが大切」になってきます。
【知識⑤】脳の勘違い×ギャンブルの演出

次に、ギャンブルを続けてしまう、「脳の勘違いとギャンブルの演出」を解説します。
今やめたら“負け確定”になる

たとえば、ギャンブルでは、負けている時、勝負は終わってみないと分からない続けて、強制的に終わるまで自分で止められなくなる場合があります。「今ここでやめたら、“負け”になってしまう」「予定していた1万使ったけど、残り1万で取り戻せばいい」といった気持ちです。
これは「損失回避バイアス」と呼ばれる心理効果で、人は得をするよりも、損をしないことのほうを優先するというバイアスです。
私たちは「100円得する喜び」よりも「100円失う痛み」のほうを2倍以上強く感じると心理学の研究でも言われています。
このように、人間はこうした気持ちになりやすい傾向があるということです。
脳を支配する演出と確立50%

ここからさらにギャンブルの演出が組み合わさります。
たとえば「ストーリー系リーチ熱い!」「赤保留きたぁ!」このような演出。
脳は、“次は当たるかも”と予想し、期待感に強く反応します。
そして、もっとも効果的にドーパミンを分泌させる大当たりの確率は50%ほどだということが研究で明らかにされており、毎回100%の確定演出のみより50%の方が依存しやすくなるということです。
ですので100%の時と比較すると、どきどきする頻度と、演出中の当たるかな当たらないかなとどきどきする時間、そして当たった時の喜びが増し総合的に分泌量が大量となります。
これは1つの大当たりで3度美味しい仕組みに作られている。つまりギャンブルの演出でドーパミンの分泌を最大限にしている。というわけです。
結論:認知がズレていく
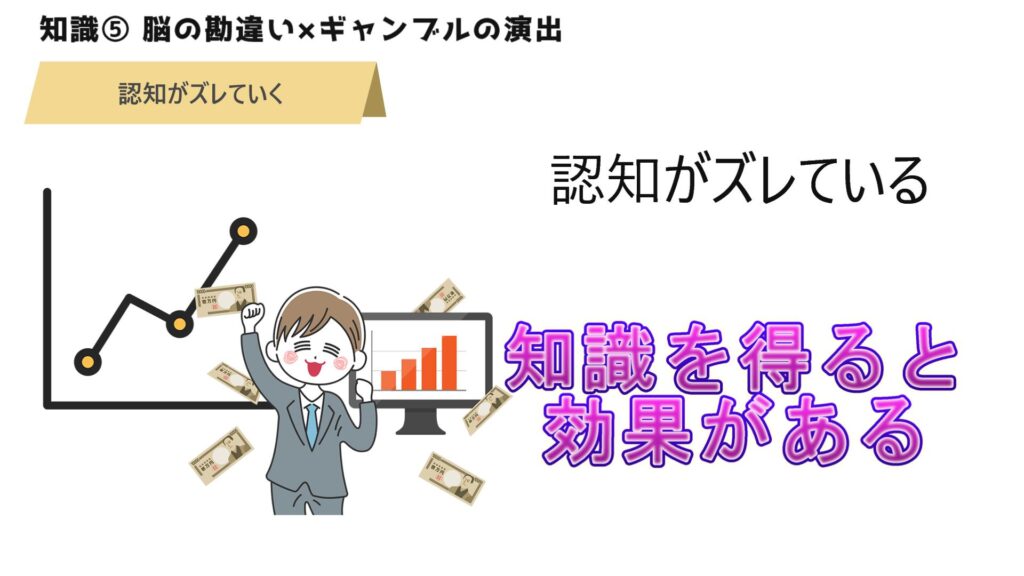
こうしたバイアスと演出によって、抜け出しずらい状況が生まれて、どんどんはまっていきます。そして脳は長期的な判断をするのが苦手ですので、お金を失っても楽しければ良いと学習し続けます。
そしてここがポイントで、現実的には負けることでも、脳が快感を記憶することで、このパターンなら勝てるとなぜか思い込んでしまうといった状態になります。
たとえば、1000回転はまっているから、そろそろ出るはず。このグラフの動きならそろそろ出るはずなど。
これを認知がズレていると呼び、このズレを修正することでギャンブルに行きたい意欲を減少させることができます。ですので、こうして知識を得て、今の自分は脳が無意識に判断していると認識するだけでも効果があります。
【知識⑥】ギャンブルは自動化されている
次に、ギャンブルは自動化されているということについて解説します。
生活水準が上がっているようなもの

ギャンブル依存症と聞くとやっかいな症状ですが、これは日常生活で例えるなら生活水準が上がっているようなものです。
日常生活では
「移動するのに電車がある」「食事をするのにコンビニがある」「お手頃価格」
このような便利な仕組みが生活水準を上げています。
これはギャンブルも全く同じで、ギャンブルは
手軽にやりやすい場所にある、手の届く価格設定、すぐに満たされる快楽、このような仕組みが「快楽の水準を上げている」
ポイント1:上がった水準は維持しないと不快になる

ここがポイントで、上がった水準は維持しないと「今更出来ないのは不便」だと思い不快になります。日常生活でいえば、一度味わった現代の生活を忘れて、サバイバルして生きていけって言われてもできないようなもの。
ですので、この不快を解消するために快楽を求めて、手軽にやれるギャンブルにまた手を出します。
ポイント2:整った環境がきっかけになる

そしてこのような仕組みが整った環境がトリガーやスイッチと呼ばれるきっかけを作り、ギャンブルがやりたくなる頻度がどんどん増えていきます。
ここもポイントで、ギャンブルをやめるにはギャンブル衝動が起こるきっかけを減らし、この「自動化」を防ぐことが重要になります。
対策には「脳の仕組み」に沿った行動がカギ
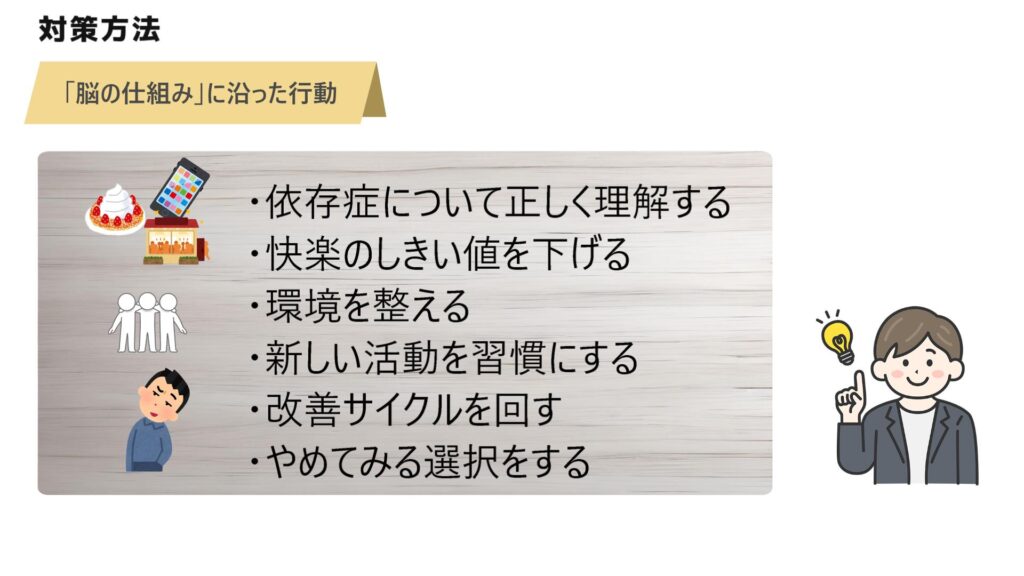
次は、対策方法を解説します。
内容としては依存の3つの要因である、依存対象、依存仲間、本人の気持ち、に対して行っていきます。
- 依存症について正しく理解する
- 快楽のしきい値(水準、レベル)を下げる
- 環境を整える
- 新しい活動を習慣にする
- 改善サイクルを回す
- 「やめてみる」選択をする
ステップ2では知識を得ることで、本人の気持ちに作用します。これは認知行動療法と呼ばれる方法の一部で、認知のズレに気付き、修正することで気持ちを変えることができます。ですので知識を得る必要とメリットがあります。
今後のステップでは、これら方法をより具体的に何をすればよいのかを解説します。ですので今回は方法というより、方針といった方が違いかもしれません。
【今回のまとめ】
それでは今回のまとめになります。
【テーマ】
今回のテーマは、正しい知識を学習することになります。
STEP2では、こうした依存の原因や対処方法を「学び」、感情的な悪循環する後悔を「論理的な納得」に切り替えることを目標にしています。
ただ厳密には今後活動をしていくうちに「納得」に変わることもありますので、なんとなく進む方向が見えたなぁくらいで、ばっちりです。
【内容】
今回の内容としては次になります。
- まずギャンブル依存と依存症では、依存の段階では、「やめよう」と思えば自分の意思でやめられる。依存症はドーパミンによる快楽を“異常に”求めるようになった状態。やめたくても脳がやめたいと思っていないから、やめられない。
- 依存の3つの要因では、要因は3つあり、1つ、依存対象があること。2つ、依存仲間がいること。3つ、本人がやめたいと思わないこと。
- 脳の3つの役割では、【意識、理性】【無意識、感情】【無意識、生存本能】の3つがある。【理性】が弱く、【感情】、【生存本能】が強い。そして意識的な思考は10%、無意識的な思考は90%で人はほとんど無意識的に考えて行動している。ポイントとして、私たちの意思と、無意識に行われる脳の判断は違う。そして無意識の方が力が強いということ。だからギャンブルから抜け出すためには、この無意識の脳をなんとかする必要がある。
- ギャンブルと脳の学習では、脳が「快感」を強く学習してしまう。予想することでドーパミンが分泌される。この分泌を繰り返すことで、脳の回路が「強化」される。ポイントとして、「やるか、やらないか」で学習は変わる。だからギャンブル依存症は「やらないことが大切」
- 脳の勘違い×ギャンブルの演出では、バイアスと呼ばれる脳が勘違いしやすい傾向がある。ギャンブルの演出でドーパミンの分泌を最大限にしている。この相乗効果で抜け出しづらい状況が生まれ、どんどんはまっていく。ポイントとして、快感を記憶して、思い込みが激しくなり、認知がズレていく。だから知識を得て認知のズレに気付くだけでも効果がある。
- ギャンブルは自動化されているでは、依存症は生活水準が上がっているようなもの。ポイントとして、一度上がった水準は、「今更出来ないのは不便」だと思い不快になる。ポイント2つ目として、整った環境がきっかけになるので、この「自動化」を防ぐことが重要。
まとめとしましては、このような内容になります。
最後に一言:他にも様々な知識がある
最後に、他にも知識としては様々なものがあります。ですがそれらを一気に知る必要はありません。今回は、ギャンブルから抜け出すのになんで知識が必要なのか、その理由が少しでも伝われば幸いです。
今後実際にギャンブルから抜け出すための方法を実施して、その合間に見るくらいで徐々に学習していきましょう。
また、今回の動画の内容はまとめ版になります。各項目の詳細は別の動画で解説していきますので、もっと詳しく知りたいかたはご覧ください。
それでは今後もこのような記事を投稿していきますので、いいなと思ったらブックマークしてくれると嬉しいです。
最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう。
関連記事
このサイトが大切にしていること
「この世界は、生きづらいものだ」と思っていた過去があります。
でも今は、そう感じていたのは“思考の回路”が乱れていただけだったんだと気づきました。
このサイト「ゆるやめ」では機械保全士として培った現実重視の“視点”をベースに、脳科学や心理学の知識そして私自身の体験を交えて、我慢ではなく緩やかな仕組みでやめるヒントをお届けしています。
よければ他の記事も覗いてみてくださいね。
参考・出典
- 厚生労働省,依存症についてもっと知りたい方へ,2025/4/21
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149274.html - 厚生労働省,依存症対策,2025/4/21
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.html